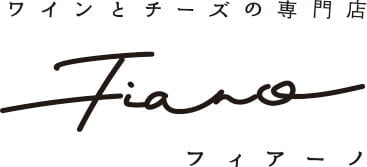チーズを食べようと思ったら「うっ、臭い!元から、こんな匂いだったかな?食べられるかな?」と思った経験はありませんか?
発酵食品であるチーズは、多かれ少なかれ独特の匂いがありますが、中には食べても大丈夫なのか判別できないものもありますよね。
また、食べられることはわかっても、臭いチーズを食べるのは苦手ということもあるでしょう。
そこで今回は「臭いチーズは食べても大丈夫なのか?おいしい食べ方は?」というテーマでお話しします。
・臭さの原因は何なのか?
・臭くても食べられるのか?
・元から臭いチーズにはどんな種類があるのか?
・臭いチーズをおいしく食べるにはどうしたらいいのか?
などをお伝えしてまいります。
チーズの匂いが、食べても平気なものなのか判断できるようになり、元から臭いチーズであれば、その匂いが気にならず食べられるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。
※なお本記事では、「臭い」の読みは「くさい」とし、「におい」という読みの表記は「匂い」とします。
チーズが臭いと感じたら、原因を突き止めよう

「臭いチーズは食べられるのか?」
この問いへの答えは、「匂いの原因による」ということになります。
どんなチーズであっても、発酵によって発生する匂いがするものです。
また、熟成させたチーズであれば、熟成により生まれる匂いもします。
これら発酵や熟成由来の匂いであれば、食べても問題ありません。
ただ種類によって匂いの程度が異なりますので、どのチーズがどのように臭いのかで、判断する必要があります。
カビが生えたり腐ったりして臭い場合には、食べると害がありますので、慎重に見極めなければなりません。
原因を突き止めて、食べられるかどうかの判別をしていきましょう。
もともと臭いチーズは発酵・熟成が原因
チーズは、原料の乳を乳酸菌の働きによって発酵させて作ります。
この時点で乳酸などが作られて、わずかに匂いが発生しますが、まだそこまで強くはありません。
このような、発酵が終わってすぐに製品化されたものが「フレッシュチーズ」です。
フレッシュチーズで有名なものは「モッツァレラ」や「マスカルポーネ」「クリームチーズ」などでしょう。
チーズを食べたいけれど臭いのがイヤならば、これらのフレッシュチーズがおすすめです。
これらは生乳と比べれば独特の匂いがあるものの、ミルクの風味が前面に出ていて臭いと感じることはないでしょう。
実際に臭いと感じるようになるのは、この後に熟成を経たチーズです。
熟成期間中にチーズの中のタンパク質や脂肪が、カビや細菌の働きによりアミノ酸や脂肪酸などに分解され、これらが増えることで匂いが強くなっていきます。
もちろん、熟成のさせ方や熟成期間により匂いのタイプや強さが変わりますので、
これらの要素も加味して、食べられるかどうかを判断してください。
後から臭くなったチーズはカビ・腐敗が原因
先ほどは、臭いチーズでも食べて大丈夫なものを紹介しました。
しかし、食べてはいけない臭いチーズもあります。
カビが生えていたり、腐っていたりして、発酵・熟成によるチーズ本来の臭さとは別の原因で臭いものは食べられません。
これらが原因で臭いチーズは、食べると体調を崩す可能性がありますので、食べるのを避けてください。
わかりやすい例を挙げると、一つが、もともと臭いわけではないフレッシュチーズが、臭くなっているものです。
フレッシュチーズは、水分が多くて傷みやすいので、臭いと思ったら傷んでいることを疑ってください。
同様に、スライスチーズや6Pチーズを代表とする「プロセスチーズ」が臭くなっている場合も、傷んでいる可能性が高いでしょう。
プロセスチーズは、製造過程で加熱加工をするので乳酸菌が死滅しており、熟成することがなく風味もほとんど変化しません。
その風味が変化しているのですから、傷んでいると考えてください。
これより念のため、傷んでいるチーズの見分け方と賞味期限、正しい保存方法についてもお伝えしておきます。
プロセスチーズとナチュラルチーズの違いについて、詳しくはこちらをご覧ください。

傷んでいるチーズの見分け方
チーズが傷む原因の大きなものは、カビと腐敗です。
それぞれの見分け方について説明します。
カビ
カビは目に見えやすく、わかりやすいでしょう。
チーズの中にはもともとカビを繁殖させているものがありますが、元からのカビ以外が新たに生えた場合は、すべて食べられないと思ってください。
ただし、カビタイプのチーズであっても、元から生えていたものと様子が異なるカビが混ざっている場合には、有害な可能性があるので、食べないようにしましょう。
一方、生えていたカビが熟成と共に増えていった場合には、食べられると思って大丈夫ですので、よく見て判断してください。
チーズのカビについて、詳しくはこちらをご覧ください。

腐敗
見た目では、表面が濡れていたり、ヌメリが出ていたり、元の色と変わっていたりすると腐っている可能性が高いです。
さらに匂いを嗅いで、元のものとは別の匂いがする場合も危険です。
アンモニアや雑巾、納豆などのような匂いを感じたらやめておいてください。
見た目や臭いに違和感がなくても、口に入れて苦みや酸味などの刺激を感じたら、やはりダメでしょう。
いずれにしても、違和感や不快感があれば危険なシグナルですので、そこで食べるのをやめてください。
チーズの腐敗について、詳しくはこちらをご覧ください。

賞味期限はあくまでも目安
チーズを購入すると、包装に「賞味期限」が記載されています。
「賞味期限」とは、味が変わらずおいしく食べられるのがいつまでかを表していて、安全に食べられるのがいつまでかを表す「消費期限」とは異なります。
比較的腐敗しにくい食品であるチーズに記載されているのは「消費期限」ではなく、この「賞味期限」です。
ですから、賞味期限内に必ず食べなければ危険だということではありません。
ただし、賞味期限が有効なのは、未開封で正しい保存方法を守った場合のみです。
開封したり、保存環境が悪かったりすると、参考にならない点はご注意ください。
まず、開封すると空気中のカビや細菌が付着します。
もし素手で触ったり、不衛生な調理器具を使ったりすれば、カビや細菌の付着する数が一気に高まります。
また、未開封であっても、温度が高いところや直射日光が当たるところに放置すれが、それもチーズにとってはダメージです。
どちらも、チーズが傷むのを早めますので、賞味期限が意味をなさなくなるのです。
賞味期限はあくまでも目安として考え、開封後の日数や保存環境を加味して、最終的には見た目や臭いなどで判断するようにしてください。
正しい保存方法で長持ちさせる
先述のとおり、未開封のほうが良い保存条件となります。
開封することで傷みやすくなるので、食べるときまで開封しないようにしてください。
また、温度が高いのも傷みやすくなるので、冬場でも冷蔵庫に入れるようにしましょう。
さらに冷蔵庫の中でも、棚の手前や扉部分は温度変化が大きいので、棚の奥の温度変化の少ないところに入れてください。
もし、食べ残した場合は、できるだけ空気と触れないようピッチリとラップをし、さらにジッパー付き保存袋に密封して冷蔵します。
この時、表面が水でぬれていると傷みやすくなるので、表面の水分はしっかり拭いてからラップをしてください。
他の食材への匂い移りも心配なので、厳重に密閉しましょう。
しばらく保存する場合は、2、3日に一度取り出して表面の滲み出る水分をふき取るとより長持ちしやすくなります。
もちろん、極力チーズに直接触らないようにし、調理器具も清潔なものを利用して、雑菌類が付着しないよう注意してください。
開封しているしていないにかかわらず、冷凍すると冷蔵保存よりも長持ちします。
ただし、解凍したチーズをそのまま食べると味が落ちてしまうので、冷凍したチーズは解凍せずそのまま加熱調理するとよいでしょう。
チーズを冷凍保存するコツについて、詳しくはこちらをご覧ください。

元から臭いチーズ、4種類を紹介

先述したように、フレッシュチーズはほとんど臭いとは感じず、ヨーグルトと区別がつかないほど爽やかなものがほとんどです。
しかし、ここから熟成により匂いが強くなっていきます。
熟成をもたらすカビや菌の種類などで匂いは異なります。
もちろん、これらのチーズが臭くても、意図して作られているものなので食べても大丈夫です。
以下に、匂いに特徴があるチーズを4種類紹介するので、「臭いけれど食べても大丈夫なチーズ」として覚えておいてください。
| 臭いチーズの種類 | 代表的銘柄 |
| ブルーチーズ | ・ロックフォール ・ゴルゴンゾーラ ・スティルトン |
| ウォッシュチーズ | ・エポワス ・マンステール ・ピエ・ダングロワ |
| 白カビチーズ | ・カマンベール ・ブリー ・シャウルス |
| ハード系チーズ | ・パルミジャーノ・レッジャーノ ・ゴーダ ・チェダー |
ブルーチーズ

ブルーチーズのブルーとは、青カビのこと。
製造途中に青かびをチーズ内に植え付け、増殖させて作ります。
この青カビから発生する匂いが特徴的で、いわゆるカビ臭さのようなものも感じますが、足の匂いのような臭さだと表現する人もいます。
しかし、臭くても腐っているわけではないですし、青カビも食べられるものを繁殖させているので、食べても大丈夫です。
ピリッと感じる苦みと強めの塩気、鼻に抜ける匂いとパンチのある旨み、これらが混然一体となり口の中を支配するので、苦手な人がいるのも確かです。
しかし、濃厚な旨みもありますので、ハマる人はハマってしまうでしょう。
今回紹介する臭いチーズの中では、最も依存性が高いといってもよいかもしれません。
「ロックフォール」「ゴルゴンゾーラ」「スティルトン」が世界三大ブルーチーズといわれており、有名です。
ブルーチーズについて、詳しくはこちらをご覧ください。

ウォッシュチーズ

ブルーチーズに負けず劣らず臭いのがこのウォッシュチーズ。
主に空気中を漂う細菌がチーズの表面に付着し、これらの働きによって、チーズを熟成させていきます。
表面の細菌の量をコントロールするために、時々表面を塩水やお酒で洗います。
ウォッシュチーズの名前はここから来ており、臭いのは主に菌が繁殖する表面です。
菌の種類は「リネンス菌」といい、納豆菌の仲間です。
たしかに、納豆のような匂いと感じるかもしれませんが、ウォッシュチーズの匂いを表現するなら雑巾のほうが当てはまるかもしれません。
もちろん、ウォッシュチーズとして販売されているものであれば、このような臭いがあっても食べられますので、安心してください。
このように、かなり強烈な匂いを持っているチーズではありますが、内側の部分はトローリとしていて、クリーミーで、とてもリッチな気分になれる味わいがあります。
日本では、今一つマイナーな感はあるけれど、臭いチーズ好きな人たちからの人気はすさまじいものがあります。
フランス産の高級チーズの代名詞である「モン・ドール」は、このウォッシュチーズです。
他にも「エポワス」「マンステール」「ピエ・ダングロワ」などが代表的なウォッシュチーズとして知られています。
モン・ドールについて、詳しくはこちらをご覧ください。

白カビチーズ

日本で人気の「カマンベール」が属するのがこの白カビチーズ。
一般的な作り方は、成型したチーズの表面に白カビを吹き付けるものです。
同じカビのチーズでも、ブルーチーズと比べると穏やかな匂いがします。
カビ臭いといえばカビ臭いのですが、きのこのようなニュアンスもあり、そこまで気にならないものも多いです。
もちろん、この白カビも食べられるものを厳選して繁殖させていますので、食べても無害です。
この白カビチーズも、ウォッシュチーズ同様、熟成と共に中がトロリとクリーミーになって、くちどけを楽しめます。
ただし、種類によっては、かなり強烈な匂いがするものもありますので、ご注意ください。
日本で流通しているカマンベールの多くは、かなりマイルドですが、本格的な白カビチーズはかなり強烈です。
マイルドなカマンベールに慣れた人は、危険な匂いだと感じるかもしれません。
もちろん、しっかりしたお店で販売されていれば、害はないので食べても大丈夫です。
もしチーズ専門店で購入するのであれば、そのような臭いものでないか確認しておくとよいでしょう。
他にも「ブリー」や「シャウルス」などが、有名で手に入りやすい白カビチーズです。
カマンベールとブリーについて、詳しくはこちらをご覧ください。

ハード系チーズ

「パルミジャーノ・レッジャーノ」をはじめ、日本でも様々な種類が出回っているハードチーズ。
カビを生やしたりせず、チーズ内部の細菌の働きなどで熟成をしていくものです。
含まれる水分量が少ないために、熟成はゆっくりと進みます。
始めのうちは匂いもそこまで強くはないのですが、熟成が長くなればそれに比例して匂いは徐々に強く、複雑になっていきます。
そのため、若いものはあまり臭いと感じませんが、熟成が長いものは臭いと感じる人もいるようです。
臭いチーズを避けたいならば若いものを購入し、臭いほうがよければ長期熟成品を購入するとよいでしょう。
ハード系チーズは他の臭いチーズのように、特徴的な匂いというわけではなく、チーズの匂いがひたすら濃縮された感じなので、臭いと思う人は少ないかもしれません。
先ほどの「パルミジャーノ・レッジャーノ」以外では、「ゴーダチーズ」「チェダーチーズ」などが有名です。
ハードチーズについて、詳しくはこちらをご覧ください。

臭いチーズのおいしい食べ方
腐ったものやカビが生えたものは食べられませんので、廃棄するしかありませんが、もともと臭いチーズであれば、食べ方によって匂いを抑えて食べやすくすることが可能です。
特に、コショウを始めとした香辛料や、バジル、ローズマリーなどのハーブ類はチーズの風味を殺さず臭みを隠すので、あらゆる種類の臭いチーズを食べやすくしてくれます。
他には、どうすればおいしく食べられるのか、臭いチーズそれぞれに合った食べ方を提案します。
ブルーチーズ
-min.jpg)
臭いチーズであっても、加熱することで匂いが飛び、食べやすくなるといわれています。
しかし、ブルーチーズを苦手だと思う人は、加熱しても食べられないのではないでしょうか。
むしろ、匂いが立ち上ることで余計に臭いと感じるかもしれません。
そこでおすすめなのが、ハチミツをかけて食べることです。
これは、ブルーチーズの定番の食べ方ですが、たしかにブルーチーズが苦手な人であっても食べられるようになるくらい、クセを抑えてくれます。
他にも、ブルーベリーやイチジクなどのジャムとの相性も抜群です。
これらはいずれも、ブルーチーズ独特の臭いを抑えるだけでなく、ピリッと刺すような刺激や強い塩気も隠してくれます。
それでありながら、うま味をしっかり感じられるので、たとえブルーチーズそのものを食べられなかったとしても一度はチャレンジしてみるべき食べ方です。
ウォッシュチーズ

ウォッシュチーズは表面が強烈な匂いを発するかわりに、中身はとてもクリーミーでおいしいチーズです。
ですから、皮を避けて中身だけ食べるとよいでしょう。
ウォッシュチーズの上面の皮をはがして、スプーンで中身をすくい、クラッカーなどに乗せて食べるとおいしいです。
丸ごとオーブンに入れて、加熱するとさらに中はトロトロのアツアツになり、うま味がグンと増します。
これをジャガイモやニンジンなどの茹でた野菜につけて食べると体も温まり、冬場には最高のおいしさです。
白カビチーズ
白カビチーズも、皮の部分にクセがありますが、中身はマイルドでクリーミーな口当たりです。
ウォッシュチーズ同様、皮をはがして中身だけを食べるというのもよいでしょう。
しかし、ウォッシュチーズほどクセは強くないので、できれば皮も食べていただきたいです。
そのためには、皮ごとオーブンで焼くとよいでしょう。
こんがりと焼き上げることで、香ばしさが出て、皮の臭みは感じなくなるはずです。
もちろん、中はアツアツ、トロトロなので気をつけて召し上がりください。
他にも、冷たいままジャムを乗せて食べるのも、臭みを感じなくなるのでおすすめです。
たっぷりのオリーブオイルと少しのコショウをかける食べ方は、3つの食材が絶妙なバランスを作り出し、フルーティな味わいを楽しめます。
ハード系チーズ

ハード系チーズは、そのまま食べるのであれば、薄くスライスすると食べやすくなります。
他にも、粉状にして料理に使うことも多いでしょう。
粉チーズであれば、おろしてから少し時間をおくと、匂いが飛んで食べやすくなります。
そのまま食べるときは、やはりハチミツやジャムをかけるとクセが気にならなくなります。
特に長期熟成したハードチーズは、スパイス類との相性もすばらしいので、コショウなどをかけて食べるのもおすすめです。
まとめ
今回は、臭いチーズでも食べて大丈夫なのかということでお話を進めてまいりました。
大事なのは、その匂いの原因が何かということです。
発酵と熟成により臭くなっているチーズであれば、食べても大丈夫ですが、カビや腐敗などで臭くなっていれば食べられません。
ですから、なぜ臭いのかを見極められるようになってください。
そこで、元から臭いチーズ4種類をご紹介しました。
これらを覚えておくと、食べられるかどうかを判別するときに役立つでしょう。
あとは、食べられるとわかっていても、臭くて食べられないということもあるかもしれません。
そんなときのために、臭いチーズの匂いを抑え、おいしく食べる方法もお伝えしました。
今回は、チーズの匂いを良くないもののように扱いましたが、フランスではチーズは臭いものであり、臭くないチーズは物足りないと思う人が多くいます。
私たちも、チーズの匂いの中に魅力を感じ、匂いと共にチーズを味わえるようになれば、チーズを楽しむ幅も広がるように思います。
安全に楽しく、臭いチーズとお付き合いしていきましょう。