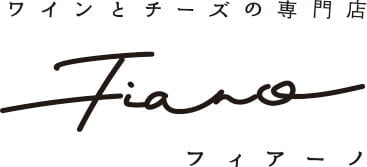「チーズは牛やヤギなどの乳を発酵させているので、腐っているのと同じだ」なんて、あなたは信じていませんよね?
たしかに、発酵と腐敗は同じような作用であり、違いは人間に害があるかないかだけという面はあります。
だからといって、チーズがすでに腐った食べ物であり、そこから腐ることはないというのは間違いです。
その証拠に、おいしく食べられていたチーズもいずれは腐り、食べられなくなってしまいます。
そのために、賞味期限も決められており、パッケージに記載されています。
では、チーズが腐るとどうなるのでしょうか?
また、賞味期限が切れた後のチーズは食べられないのでしょうか?
今回はこれらの疑問に答えるとともに、チーズが腐りにくい保存方法や腐ったチーズは食べられるのか、といったことについても説明してまいります。
食べるのを忘れて、かなり時間が経ってしまったチーズがあるけど大丈夫かな?というときの参考になりますので、ぜひ最後までお読みください。
チーズが腐るとどうなるの?臭いや味の変化は?
冒頭で発酵食品であるチーズも、腐るというお話をしました。
チーズの種類や保存方法などにより腐るまでの期間は異なりますが、どのようなチーズであれ、いずれは腐るものと考えてよいでしょう。
では、実際に腐ったチーズというのはどのようになってしまうのでしょうか?
チーズが腐ると、そのサインが見た目・臭い・味に表れます。
もちろん、そのすべてに表れるとは限りませんが、いずれかにサインが表れていれば腐敗を疑ったほうがよいでしょう。
腐ったチーズのサインがどう表れるのか、それぞれについて見ていきましょう。
見た目

購入直後の見た目から何かしらの変化があれば、腐っている可能性が高いと考えられます。
いくつかのパターンがありますので、それぞれ見ていきましょう。
カビ
わかりやすいのが、黒色や白色、青色、赤色といったカビが生えている場合です。
カビと腐敗は異なりますが、カビが生えているということは、保存環境がよくなかったり、保存期間が長かったりするわけなので、腐っていることも疑ってみるべきです。
なにより、カビが生えている時点で食べることは危険です。
カビのすべてが毒素を持っているわけではありませんが、毒があり食べると体調を崩す場合もあります。どちらか判断するのは難しいので、いずれにしても食べないようにしてください。
ただし、ブルーチーズや白カビチーズなどに元から生えているカビは食べられます。もし、元のカビが熟成とともに増えているのであれば、問題ないでしょう。
元からのものとは異なるカビは注意深く見れば、色が違っていたりして区別がつくはずです。
違う種類のカビが生えているのを発見したら、あきらめて捨てるようにしてください。

乾燥

表面が乾燥している場合も気をつけましょう。
乾燥自体が腐敗の表れというわけではないのですが、特に色が茶色くなっている場合には、開封してから相当な期間が経っているはずです。
その間に腐ってしまっている可能性が高いですし、食べたところでおいしくなくなってもいるでしょうから、口にしないようにしてください。
ヌメリ

表面が濡れてヌルヌルした感じがあれば、それも危険な合図です。
特に、表面を触ってみて糸を引くようであれば、腐っていることは間違いないでしょう。
この場合も、食べようとはせず、速やかに処分してください。
臭い
発酵食品であるチーズには、どのような種類のものであっても多少なりとも独特の臭いがあります。
ただし、チーズ本来の臭いであれば、比較的シンプルでそこまで不快には感じないはずです。
というのも、製造時に使用される限られた菌やカビが発する臭いしかしないからです。
しかし腐敗臭となると、周りの環境下に生息する様々な雑菌が臭いの原因となりますので、ぞうきんのようないろいろ混じった臭いになります。しかも、アンモニアを代表とする不快な臭いも混じってきます。
このような臭いをかぐと、体が自然と「食べてはいけない」という反応をするはずです。
自らの感覚に従って、無理に食べないようにしてください。
味

見た目と臭いでは気づかず、腐ったチーズを口にするとどうなるのでしょうか?
もし、腐っていない状態の味を覚えていれば、その時の味から変化していることに気づくでしょう。
特に「苦い」「すっぱい」といった味の変化が、より強く感じられるでしょう。
ただし、チーズの種類によっては元から苦み・酸味を持つものもありますし、熟成によって増すこともあります。この場合は、必ずしも腐っているとはいえず、判断をするのはむずかしいものです。
嫌な刺激や不快感があるようでしたら、腐っていると考えるのがよいでしょう。
賞味期限切れのチーズは食べられない?

一般的にチーズを購入すると、パッケージには賞味期限が記載されているはずです。
では、賞味期限を過ぎるとそのチーズは腐るのでしょうか?
賞味期限と腐ることの関係についてお話します。
賞味期限と消費期限は異なる
まず明らかにしておきたいのが「賞味期限」と「消費期限」の違いです。
これらは似たような響きがする言葉で、混同して使用することもよく見受けられます。
しかし、両者は明確に区別すべきものですので、ここではっきりさせておきましょう。
賞味期限
賞味期限とは「おいしく食べられる期限」という意味であり、未開封で正しい保存方法をとっていれば、この期限までは味の変化もほとんどなく、当然腐敗の心配もありません。
賞味期限は、ある程度傷みにくい食品に記載されるもので、設定されている期間は比較的長めです。
ですから、この期限を過ぎたからといってすぐに食べられなくなるというわけではなく、保存状態が良ければ、それからしばらくは安全に食べられるとされています。
ただし、あくまでも未開封かつ推奨する保存方法を守っている場合であり、開封したものに関しては賞味期限は無効となります。
たとえ賞味期限まで日にちがある場合でも、開封後は速やかに食べるようにしてください。
消費期限
一方、消費期限とは「過ぎたら食べないほうがよい期限」という意味です。比較的傷みやすい食品、つまり腐りやすい食品に記載されており、期間も短めに設定されています。
未開封であっても消費期限を過ぎると腐る危険が高くなりますので、賞味期限とは異なり、安全のためには比較的シビアに守るべきものです。
チーズの賞味期限・消費期限の見分け方
賞味期限と消費期限の違いをご理解いただけたと思いますが、一般的にチーズに記載されているのは賞味期限です。
ですから、いわゆる生ものに比べると腐りにくい食べ物だということです。
しかし、先ほど説明したように、賞味期限とは未開封の状態が条件なので、一旦封を切ったチーズに関しては、記載された期限は参考にならないと思ってください。
そこで、開封後のチーズに関しては、自ら消費期限を見極める必要があります。
そして、消費期限はチーズの種類によって異なりますので、各チーズの消費期限の目安を覚えておいてください。
ナチュラルチーズ
基本的に原料乳を加熱する以外に、途中で加熱せず製造するのがナチュラルチーズです。
発酵後の乳酸菌も活きているため、作られた後も熟成が進み、状態が変化しやすくなっています。
しかし、ナチュラルチーズの中でも、種類による賞味期限の差が大きくあります。
以下が代表的なナチュラルチーズです。
| タイプ | チーズ名 |
| フレッシュ | ・モッツァレラ ・マスカルポーネ ・クリームチーズ ・リコッタ ・カッテージチーズ |
| 白カビ | ・カマンベール ・ブリー |
| 青カビ | ・ロックフォール ・ゴルゴンゾーラ ・スティルトン |
| ウォッシュ | ・エポワス ・タレッジョ |
| ハード・セミハード | ・パルミジャーノ・レッジャーノ ・ゴーダ ・ペコリーノ・ロマーノ ・エダム ・グラナ・パダーノ ・チェダー ・エメンタール |
この中でも、フレッシュタイプのチーズは、水分が多く塩分は低めのため長期保存に向きません。
とくに、開封後は牛乳などと変わらず、消費期限は2~3日と考えるとよいでしょう。
一方で、水分が少なく、塩分が高めのハードチーズなどは日持ちがしやすいです。
未開封時のように長期の保存はできませんが、保存状態が良ければ、10日前後を消費期限とみてよいでしょう。
また、腐敗が急速に進むものではありませんので、多少おおらかに考えてもよいでしょう。
白カビ・青カビ・ウォッシュタイプは、フレッシュとハードの中間と考えてください。
プロセスチーズ
プロセスチーズの中で認知度が高いものを挙げれば、以下のとおりです。
・6Pチーズ
・スライスチーズ
・とろけるチーズ
・さけるチーズ
このように、スーパーなどで多くの種類が売られていて、私たちに馴染みがあるのがプロセスチーズです。
プロセスチーズは、ナチュラルチーズなどを加熱して加工してありますので、ナチュラルチーズと比較すると状態の変化が起こりにくいチーズといえます。
もちろん、製品により賞味期限は異なるものの長期保存が可能です。
とはいえ、開封するとやはり早めに食べなければならないのは、ナチュラルチーズと同じです。
フレッシュチーズのように、数日で消費しなければならないことはありませんが、やはり10日前後を消費期限として食べ切るようにしてください。
チーズが腐りにくい保存方法

それでは、チーズを腐りにくくするには、どのように保存したらよいのでしょうか?
まず言えるのは、常温での保存は避けるべきです。
一般的にチーズは冷蔵保存を前提として賞味期限が設定されており、常温での保存は推奨されていません。
温度が高いと傷みやすくなりますので、必ず冷蔵温度以下で保存しましょう。
以下では、冷蔵と冷凍それぞれの保存する際のポイントをお伝えします。
冷蔵保存
どのチーズであっても未開封であれば、冷蔵保存で賞味期限までおいしく食べられます。
賞味期限内に食べるのであれば、そのまま冷蔵庫に入れておいてください。
もし、開封した後に冷蔵庫で保存するのであれば以下のようにしましょう。
1.チーズの表面の水分を清潔なキッチンペーパーでふき取ります
2.できるだけ空気に触れないよう、ピッチリとラップで包みます
3.さらに、空気を抜くようにしてジッパー付き保存袋に入れます
4.あまり温度が変化しないよう、野菜室などの奥にしまいます
ただし、先述したように開封後の長期保存はできませんので、早めに食べてください。
冷凍保存
チーズは種類によっては冷凍保存が可能です。
もし賞味期限に食べ切れないのであれば、冷凍保存をしてみましょう。
ただし、種類によっては、解凍すると風味が落ちておいしく食べられなくなりますので、冷凍するのは加熱して食べるものにしてください。
未開封のチーズであれば、そのまま冷凍するのが最も長く保存できますので、開ける必要がなければ、そのまま冷凍庫の奥の温度変化が少ないところにしまいましょう。
逆に、開封した後のチーズを冷凍する場合は、少し手間をかけたほうがよいでしょう。
冷凍と解凍を繰り返すたびに状態が悪くなっていきますので、以下のようにしてください。
1.一度に使い切れる量に小分けにします
2.それぞれを、きっちりとラップで包みます
3.空気を抜くようにしてジッパー付き保存袋に入れます
4.温度変化しづらい、冷凍庫の奥にしまいます
使う時は、その日に食べる分だけを冷凍庫から出して、解凍せずに加熱調理すれば、おいしく食べられます。

腐ったチーズを食べたら食中毒になる?
もし腐っていることに気づかずチーズを口にしてしまったら、どうしたらよいのでしょうか?
口にして腐っていると感じたら、すぐに吐き出してください。
そうすれば、その後体調を崩すまでにはならないはずです。
しかし、そのまま飲み込んでしまったらどうなるのでしょうか?
その場合は、いわゆる食中毒の症状である
・腹痛
・嘔吐
・下痢
などが出る可能性があります。
もちろん、腐敗の進み具合や食べた量などによって、かならず症状が出るわけではありません。
ですから、しばらくは様子を見てもよいでしょう。
しかし、少しでも体調が悪くなっている気がしたら、速やかに医院へ行くことをおすすめします。
この時に気をつけていただきたいのは、嘔吐や下痢の症状を薬で抑えないことです。
体が排出しようとしている毒素を体内にとどめてしまうことになるため、症状がより悪化する危険性があります。
出せるものはすべて出してしまうことを基本と考えましょう。
腐ったチーズは加熱すると食べられる?
基本的には、腐ったチーズは加熱しても食べられないと思っておきましょう。
加熱することで無毒化されて食べられるようになるという意見もありますが、加熱しても無毒化されない場合があるからです。
食中毒菌やカビの中には猛毒を発生し、命にかかわるものもありますので、決して軽く見ないでください。
仮に加熱により無毒化できたとしても、臭いや味はもとには戻らないため、そもそも食べてもおいしくないでしょう。
腐ってしまったと思ったらあきらめて、速やかに廃棄することをおすすめします。
まとめ
今回は、チーズが腐るとどうなるのか、ということでお話してきました。
発酵作用により作られているチーズであっても、腐るという現象は起こります。ただ、種類がいろいろとあるため腐敗の状態も様々であり、それらを一言で表現するのは難しいものです。
とはいえ、注意深く見れば、見た目や臭い、味などでわかるでしょう。
また、賞味期限も未開封時の目安であり、開封後は個別に判断するしかありません。
腐りにくくするのであれば、保存方法にも気をつけてください。
腐ったチーズを誤って食べてしまうと食中毒になる危険性がありますし、加熱したから大丈夫というわけでもありません。
まずは、腐る前に食べることを心がけてください。