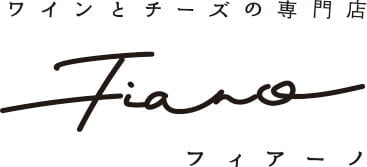「ゴーダチーズ」といえばスーパーでも見かけることが多いセミハードタイプのチーズです。
しかし、カマンベールやゴルゴンゾーラなどと比べるとやや特徴がわかりづらく、「どんな味?」と聞かれて即答できる人は少ないのではないでしょうか。
そこで今回は、馴染みはあるけど控えめな存在のゴーダチーズのことをじっくり解説してまいります。味の特徴や産地、作り方、食べ方、合うワインなどをお伝えします。
ゴーダチーズがグッと身近に感じられるようになりますので、ぜひ最後までお読みください。
ゴーダチーズとは?

ゴーダチーズは世界中で作られているため生産量が多く、スーパーでもよく見かけるほどの人気のチーズです。
しかし、味の特徴や産地などについてはあまり知らないのではないでしょうか。
まずは、ゴーダチーズの基本的な情報から見ていきましょう。
ゴーダチーズ
| 原料 | 主に牛乳 |
| 種類 | セミハード |
| 固形分中の乳脂肪 | 48%~ |
| 原産国 | オランダ |
| 味の特徴 | クセがなくやさしい風味。 熟成するにつれて、複雑になり旨味が増す |
ゴーダチーズの味の特徴

ゴーダチーズの味の特徴を一言で表すなら「マイルド」となるでしょう。
ブルーチーズやウォッシュチーズなどの強烈な特徴を持ったものと比べると非常に穏やかな味わいで、チーズに不慣れな人であっても食べやすいと感じるはずです。
私たち日本人にとって最も馴染みがあるチーズといえばプロセスチーズですよね。
ゴーダチーズはプロセスチーズの原料として使われることが多いので、どことなく味も似ていて、抵抗なく食べられるのではないでしょうか。
かといって、味に特徴がないわけではありません。ゴーダチーズは乳脂肪分が比較的高いので、熟成されていないものはミルクのフレーバーがしっかりしています。
しっとりとした食感と相まって、凝縮したミルクのクリーミーなおいしさを感じられるでしょう。
さらに、ゴーダチーズは熟成も楽しめます。熟成期間が長くなるほど味わいは凝縮していき、ナッツなどを感じさせる複雑な香りとアミノ酸由来の豊かな旨味が前面に出てきます。
濃く茶色みを帯びた見た目や組織が締まって硬くなった食感からも熟成の程度を感じられるはずです。
熟成期間の違いによる選択肢があるのも、ゴーダチーズの特徴です。
ゴーダチーズの産地と製法
ゴーダチーズはいまや世界中で製造されており、パッケージを見ると日本やデンマーク、ドイツなど様々な生産地のものを見かけますが、原産地はオランダです。
また、ゴーダチーズといえば「カードウォッシング」という製法が特徴となっています。
それぞれについて、掘り下げていきましょう。
ゴーダチーズはオランダ原産
ゴーダチーズは、オランダ・ロッテルダム近郊の「ゴーダ村(オランダ語では「ハウダ」と発音)」で作られ始めたとされています。
オランダのチーズ作りの歴史は紀元前までさかのぼれるものの、このゴーダチーズは13世紀ごろから生産されているようです。
その後ヨーロッパ各地で評価が高まり、輸出に向くように改良されていきました。
その結果さらに人気が上がり、今ではオランダ産チーズの半分以上を占めるまでになっています。
現在、一般に出回っているゴーダチーズのほとんどは工場において、殺菌乳で生産されているものです。
しかし、オランダの農家で作られたものや無殺菌乳で製造されたものといった、特徴的な製品も一部で販売されています。
ゴーダチーズの奥深さを追求するのであれば、チーズ専門店でこれらを探してみるとよいでしょう。
特徴的な製法「カードウォッシング」とは?
ゴーダチーズは、「カードウォッシング」という特徴ある製法がとられています。ゴーダチーズらしい特徴を生み出しているのがこの工程です。
一般的なゴーダチーズの原料は牛乳です。温めた牛乳に、乳酸菌と凝乳酵素を加えると凝固していきますが、このときの固形分が「カード(凝乳)」です。
カードウォッシングとは、このカードを湯で洗うことを指しています。
洗うことで、カード内に残っていた乳糖の濃度が下がります。乳糖は雑菌のエサとなるため、乳糖を減らすことで腐敗リスクを抑えて保存性を高めることが可能です。
ゴーダチーズの特徴の弾力あるしっとりした食感がなぜ得られるかというと、このカードウォッシングにより乳酸発酵が穏やかに進み、チーズの収縮が抑えられるからです。
その後は型に詰めて、プレスすることによって水分を排出し、熟成を経て製品化されます。
ちなみにフランス語では、カードウォッシングの効果面に着目して「デラクトザージュ(乳糖除去)」と呼びます。
ゴーダチーズの食べ方
-min.jpg)
ゴーダチーズは、販売されている状態によっては切り方に注意が必要です。
どのように切るとよいのかについてお伝えします。また、一般的にはどのような食べ方をされているのかについても説明します。
ゴーダチーズは切り方に注意
スーパーで売られているゴーダチーズは小分けにされているため、それしか見たことがなければ想像がつかないかと思いますが、元のゴーダチーズは直径35cm、高さ11cm、重さ約12gの円盤型をしています。
また、ほとんどの場合、表面が黄色いロウによって覆われています。
もし大きな塊で売られていれば、一部にこのロウが残っていることがありますので、その場合は食べる前にロウを取り除かなければなりません。
加えて、表面に近い部分は中心と比べると硬くなっています。
硬くても食べられるのですが、中心部よりもおいしくないと感じるのが普通でしょう。
ですから、この硬い部分がカットしたものにバランスよく入るように切り分けるようにしてください。
もし硬い部分を食べたくないのであれば、切り落として保存しておき、後日料理に使うのもおすすめです。
もっとも、スーパーなどで見かける数百グラム程度のものは、ロウは残っていません。
また若いものであれば表面もほとんど硬くなっていませんので、切り方に注意する必要はないでしょう。
もしかしたら「リンドレスゴーダ」と表記されているものを見かけることがあるかもしれません。
これは表皮がないゴーダチーズのことなので、これも切り分けるときに上記のような注意は不要です。
様々なチーズの切り方についてもっと詳しくお知りになりたければ、こちらもご覧ください。

ゴーダチーズのロウ(ワックス)について詳しくはこちらをご覧ください。

ゴーダチーズのおいしい食べ方
ゴーダチーズはマイルドな味で食べやすいため、様々な食べ方ができます。ここでは代表的なものを紹介しますが、ゴーダチーズの味わいを活かしたオリジナルの食べ方にもチャレンジしてみてください。
そのまま食べる
ゴーダチーズはそのまま食べてもおいしいチーズです。先述したとおり、ロウを残さないようにし硬い部分に気をつければ、後は好みの大きさに切り分けるだけです。
生のフルーツやドライフルーツ、ナッツ類とも相性が良いので、一緒にお皿に盛り付けるとそれだけで食卓を飾る一品になるでしょう。
さらにおいしく食べるコツは、食べる30分前に冷蔵庫から出しておくことです。
常温のほうが、冷たい状態よりもチーズの香りやコクが感じられるでしょう。
生のフルーツとチーズの相性についてもっと詳しくお知りになりたければ、こちらもご覧ください。

ドライフルーツとチーズの相性についてもっと詳しくお知りになりたければ、こちらもご覧ください。

失敗しないチーズの盛り付け方をお知りになりたければ、こちらもご覧ください。

オシャレな「チーズの盛合わせ」の作り方をお知りになりたければ、こちらもご覧ください。

加熱しない料理に使う
ゴーダチーズをスライスしてパンに挟みサンドイッチにしたり、キューブ上にカットしてサラダに入れたりするのもおすすめの食べ方です。
ミルクの爽やかな味わいがあるゴーダチーズの個性が、それぞれの料理のアクセントとなります。
この場合は、熟成していないものがよいでしょう。
加熱する料理に使う

ゴーダチーズは温度が上がると溶けますので、加熱する料理に使用すると見た目で感じるおいしさもアップさせられます。
もちろん、クリーミーな味わいがコクを加えますので、料理のグレードもワンランク上がるでしょう。
ピザやグラタンの上に乗せて焼いたり、オムレツの中に入れたりと様々な使い方が可能です。
また、近年ご家庭でも楽しまれるようになったチーズフォンデュにするのもよいでしょう。
チーズフォンデュといえば、一般的にはエメンタールチーズやグリュイエールチーズを使いますが、ゴーダチーズを使うことでオリジナルな味わいを堪能できます。
ゴーダチーズに合うワイン

チーズといえばワインが思い浮かぶほど、両者は切り離せない関係です。
もちろん、ゴーダチーズもワインのお供にピッタリです。
しかも、若いうちの穏やかでフレッシュさも感じる味わいから、熟成を重ねるにつれて複雑さや深みを増していくという特徴がありますので、熟成度に応じて合わせられるワインの幅も広くなっています。
それぞれ、どのようなワインとの相性が良いのか見ていきましょう。
| ゴーダチーズの熟成度合い | 合うワイン |
| 製造直後 | カジュアルな白ワイン、爽快なスパークリングワイン |
| 少し時間が経過 | しっかりした白ワイン、シャンパン |
| 浅い熟成 | ライト~ミディアムボディの赤ワイン |
| 長期熟成 | フルボディの赤ワイン |
若いゴーダチーズに合うワイン

クセが少なくミルクの優しい風味が感じられる若いゴーダチーズは、辛口の白ワインと合わせると互いの特徴を引き立て合うでしょう。
製造後間もないフレッシュ感の目立つものには、カジュアルな白ワインや爽快なスパークリングワインでペアリングしてみてください。
ゴーダチーズのふわりと漂うバターのような香りとワインの爽やかな果実味が、絡み合って余韻へとつながるはずです。
ゴーダチーズは、時間が経つほどに旨味が増していき複雑な味わいになっていきますので、時間の経過に合わせてワインもしっかりしたものにするとよいでしょう。
ですから、熟成感が出始めているものにはしっかりした白ワインを、もしくはシャンパンのように熟成香のあるスパークリングワインを相手に選ぶとバランスが良くなります。
熟成したゴーダチーズに合うワイン

若い頃のようなミルキーさがなくなり、動物性の旨味を感じさせる風味が目立つ熟成したゴーダチーズは、赤ワインとの相性が良くなっています。
熟成が比較的浅いうちは、軽めの赤ワインと合わせるとよいでしょう。
チーズとワインが互いの旨味を引き出しあい、絶妙なコントラストを楽しめます。
ゴーダチーズの熟成が進んで枯れた味わいを感じさせるほどになっていれば、フルボディの赤ワイン、もしくは熟成感のある赤ワインとともに味わってみてください。
両者のポテンシャルが最大限に発揮されて、特別なマリアージュ体験となるはずです。
チーズとワインの相性についてもっと詳しくお知りになりたければ、こちらもご覧ください。

まとめ
今回は、馴染みがありながらも深くは知られていなかったであろうゴーダチーズについてお話しました。
あまり個性を主張しない、オランダ原産のこのチーズの味の特徴や製法、食べ方、相性の良いワインなどをご理解いただけたでしょうか。
スーパーでも買える手軽さに加えて、そのまま食べてよし料理に使ってよしの使い勝手、さらに熟成度に応じて様々なワインに合わせられる守備範囲の広さなど、魅力を十分にわかっていただけたかと思います。
これまであまり目立たなかったゴーダチーズを、これからもっと楽しんでいただけるとうれしいです。