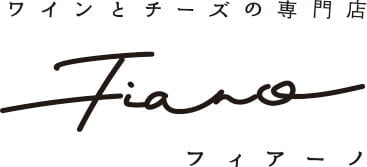「カッテージチーズはヘルシー!」
あなたも、こんなことを聞いたことありませんか?
実は、カッテージチーズは数あるチーズの中で最もサッパリしていて、最もカロリーが低いのです。
それなのに、他のチーズとほぼ変わらないくらい、栄養成分もしっかりあります。
ですから、ヘルシーというのは間違いありません。
ということで、ダイエット中の人や普段から食事の栄養を気にする人にもピッタリです。
今回は、そんなカッテージチーズについて
・どんなチーズなのか?
・おいしい食べ方は?
・簡単に手作りする方法とは?
・カッテージチーズの保存方法は?
といった内容を、お伝えします。
「チーズは食べたいけど、カロリーや脂質が気になる」というときにおすすめな理由もわかりますので、ぜひ最後までお読みください。
カッテージチーズとはどんなチーズ?

まずは、カッテージチーズとはどんな種類のチーズなのか、どうやって作られるのかを見てみましょう。
カッテージチーズがヘルシーだといわれる理由、ダイエットに向いているとされる理由もお伝えします。
カッテージチーズは、ナチュラルチーズの中のフレッシュチーズの一種
カッテージチーズとは、一般的に牛乳から乳脂肪分を除去した脱脂乳から作られる、やわらかな食感のチーズ。
かすかに酸味のする優しい味わいで、ほとんどクセがないため、料理やスイーツ、ワインのお供など幅広く使えます。
「ナチュラルチーズ」という種類の中の一つである、「フレッシュチーズ」に分類されます。
カッテージチーズの個性を理解しやすくするため、チーズの種類と製法について簡単に説明しておきましょう。
チーズには、ナチュラルチーズとプロセスチーズがある
ご存知かと思いますがかと思いますが、チーズは大きく2つの種類に分かれています。
どちらも同じように販売されているものですが、製法などが異なっています。
それぞれのタイプについて見ていきましょう。
ナチュラルチーズ
牛などのミルクを乳酸菌や凝乳酵素(レンネットと呼ばれる)で凝固させて、カード(凝乳)、とホエイ(乳清)に分けて、カードを製品化したもの、または熟成させて製品化したものです。
一般的に、乳酸菌が活きたまま残っているので、時間と共に熟成していくことで味も変化します。
また、非熟成タイプと熟成タイプの特徴が異なる2タイプがあり、熟成タイプはさらに白カビチーズやブルーチーズなどに細かく分類されます。
プロセスチーズ
ナチュラルチーズに乳化剤などを加えた後、加熱して溶かして、再び成形したものです。
加熱することで乳酸菌は死滅し、熟成することはありません。
その代わり品質は安定するので、長期保存が可能となっています。
戦後の日本で、先に広まり始めたのがこれらプロセスチーズであり、スライスチーズや6Pチーズなどスーパーで目にする機会が多いでしょう。
ナチュラルチーズとプロセスチーズの違いについて、詳しくはこちらをご覧ください。

フレッシュチーズであるカッテージチーズの作り方
先述したナチュラルチーズの作り方をしますが、原料には脱脂乳を使用するという特徴があります。
できあがったカードを、ホエイが分離しやすいように糸でカッティングし、さらに加熱します。
するとカードが粒状になるので、それを水洗いし、水を切ったものがカッテージチーズです。
これが一般的な作り方ですが、このままだとポロポロとしたそぼろのような食感なので、これを裏ごしして、なめらかな口当たりにしたものも生産されています。
フレッシュチーズとは、ナチュラルチーズの中でも、このように熟成させず製品化したもののことです。
フレッシュチーズは、他に「リコッタ」「モッツァレラ」「マスカルポーネ」などが代表的です。
カッテージチーズをさらに深掘りすると…
カッテージチーズの産地については説が分かれていて、イギリスともオランダともいわれています。
最初は自然に酸敗した乳から作られたとされ、最もシンプルで世界最古のチーズの一つです。
「カッテージ」の名は、英語で山小屋を意味する「cottage(コテージ)」であり、元々農家などの小屋で作られていたことが由来となっています。
お腹がゴロゴロする原因となる乳糖はほとんどがホエイに含まれており、ほとんどのホエイを排出させて作られる、他のチーズを食べてお腹がゴロゴロすることはありません。
しかし、カッテージチーズは凝乳時間が短いため、乳糖が2~3%ほど残っており、乳糖不耐症の人には合わない可能性があるので、注意して食べるようにしてください。
ちなみに、先述したリコッタチーズも、同じフレッシュチーズで見た目も似ているため、カッテージチーズと混同されることが多いようです。
しかしリコッタは、ホエイを加熱して作られるため特殊であり、カードを製品化する他のチーズとはまったくの別物です。
カッテージチーズ
| 種類 | フレッシュタイプのナチュラルチーズ |
| 原料乳 | 牛乳(脱脂乳) |
| 原産地 | イギリスorオランダ |
| 見た目の特徴 | そぼろのようにポロポロとした食感 ※裏ごしした滑らかなタイプもあり |
| 味の特徴 | サッパリした軽い味わいとさわやかな酸味 |
カッテージチーズは四拍子そろったダイエット食品

冒頭でカッテージチーズがヘルシーだといわれていて、その理由としてカロリーは低いのに栄養は十分にあるからだとお伝えしました。
これをもう少し詳しく説明しますと、他にも糖質と脂質が低く、タンパクが豊富に含まれているという理由もあります。
このように、栄養面で好ましい条件が四拍子そろっているから、現代の多くの人、特にダイエット中の人にピッタリな、ヘルシーな食品なのです。
これらの栄養に関する四要素について述べてまいります。
低カロリー
カッテージチーズの栄養について、特筆すべきはこのカロリーの低さでしょう。
商品にもよりますが100gあたり99キロカロリー程度であり、馴染みのあるカマンベールチーズの291キロカロリーや、プロセスチーズの313キロカロリーと比べると圧倒的に低カロリーです。
脱脂乳が原料となっているため、取り除かれた脂質の分だけカロリーが抑えられています。
そもそもチーズそのものが、通常の食べる量を考えればそこまで高カロリーとはいえません。
そこからさらに、カロリーが低くなっていることは、大きな魅力でしょう。
低糖質
糖質に関しても、100gあたり1.9gのカッテージチーズは、チーズの中では低いグループに入っています。
そもそも、チーズは全体的に低糖質の食品です。
食後の血糖値の上がり度合いを表す指標として、食品には「GI(ジーアイ)」が定められています。
GI値が高い食品ほど食後の血糖値が上がりやすいとされていますが、チーズはおよそ30~35です。
55以下が低GI食品に分類されますので、GI値の点でもチーズのメリットは大きく、カッテージチーズはその中でも低いので、かなりヘルシーといってよいでしょう。
チーズの糖質について、詳しくはこちらをご覧ください。

低脂肪
脱脂乳を原料とするカッテージチーズが、低脂肪であるのは当然ですよね。
それでも、他のチーズと比較すると、あまりにも脂質量が少ないので驚かれると思います。
カッテージチーズ100g中の脂質はおよそ4.5gです。
これに対し、次に脂質が少ないリコッタチーズでも11.5gと倍以上もあるのです。
さらに、脂質が最も多いチェダーチーズともなると33.8gもあり、なんと7.5倍以上にもなってしまいます。
このように、脂肪分が少ないにもかかわらず、タンパク質をはじめとした栄養素の多くが残っているので、カッテージチーズがダイエット中や健康を気にする人たちに人気があるのもうなずけるでしょう。
チーズの脂質について、詳しくはこちらをご覧ください。

高タンパク
カッテージチーズ100gに含まれるタンパク質はおよそ13.3gです。
44.0gも含むパルミジャーノ・レッジャーノには及びませんが、マスカルポーネの4.4gやリコッタの7.1gと比べれば十分な量といえるでしょう。
タンパク質は、私たちの体の細胞を構成する栄養素であり、不足すると新陳代謝が円滑に行われません。
また、体の機能維持に必要なホルモンなどの、原料となる栄養素でもあります。
ですから、タンパク質が不足すると、筋力が衰えるだけでなく、体の機能も低下し、体調を崩しやすくなってしまいます。
肌や髪の毛のターンオーバーも順調に行われず、美容面でも悪影響が出ますので、ダイエット中には特にカッテージチーズでタンパク質を摂取するとよいでしょう。
チーズの栄養(100g中)
| 種類 | 名称 | カロリー (kcal) | 糖質(≒炭水化物) (g) | 脂質 (g) | タンパク質(g) |
| ナチュラルチーズ | カッテージ | 99 | 1.9 | 4.5 | 13.3 |
| エダム | 321 | 1.4 | 25.0 | 28.9 | |
| エメンタール | 398 | 1.6 | 33.6 | 27.3 | |
| カマンベール | 291 | 0.9 | 24.7 | 19.1 | |
| クリーム | 313 | 2.3 | 33.0 | 8.2 | |
| ゴーダ | 356 | 1.4 | 29.0 | 25.8 | |
| チェダー | 390 | 1.4 | 33.8 | 25.7 | |
| パルミジャーノ | 445 | 1.9 | 30.8 | 44.0 | |
| ブルー | 326 | 1.0 | 29.0 | 18.8 | |
| マスカルポーネ | 273 | 4.3 | 28.2 | 4.4 | |
| モッツァレラ | 269 | 4.2 | 19.9 | 18.4 | |
| シェーブル | 280 | 2.7 | 21.7 | 20.6 | |
| リコッタ | 159 | 6.7 | 11.5 | 7.1 | |
| プロセスチーズ | 313 | 1.3 | 26.0 | 22.7 | |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
カッテージチーズのおいしい食べ方

カッテージチーズはそのまま食べてもおいしいのですが、料理やスイーツなどにも使え、幅広く楽しめます。
もちろん、ワインと合わせるのもOK。
守備範囲の広さに驚きます。
そんな、おいしい食べ方、合わせるワインについてお伝えします。
いろいろできるおいしい食べ方
シンプルに、リンゴ、バナナ、キウイなどの果物に乗せるだけでおいしく食べられます。
果物には、チーズに含まれない栄養素のビタミンCが多く含まれているため、おいしくて栄養のバランスもとれて一石二鳥です。
また、カッテージチーズはサッパリしているので、甘みのあるジャムやハチミツなどをかけるとさらにおいしくなります。
もちろん、クラッカーやパンなどにディップするのもOKで、ブラックペッパーをかければ、ワインのお供にもバッチリです。
カロリー、糖質、脂質共に低いので、夜遅くにおつまみが欲しいときにはピッタリですね。
もちろん、サラダに入れるのも定番中の定番。
上からかけても、野菜と和えても、ドレッシングに入れても、どんな使い方でも野菜のおいしさを引き立ててくれます。
他にも、温かい料理にだって幅広く使えます。
パスタに入れたり、かけたりすれば、味に深みを出せますし、シチューなどの煮込み料理にもコクを出すために加えるとよいでしょう。
当然、スイーツにも使えます。
チーズケーキやティラミスなど、カッテージチーズを使えばよりヘルシーにできますよ。
定番の食べ方だけでなく、工夫次第で様々な楽しみ方ができますので、ちょっと冒険した料理を作ってみるのも面白そうですね。
合わせるワイン

あっさりとしていて爽やかな酸味があるカッテージチーズには、軽めの白ワインが合いやすいでしょう。
甘みがあるワインとも、一緒に楽しめます。
もちろん、スパークリングワインとも相性が良く、合わせるならカジュアルなものがよいでしょう。
もし、赤ワインを飲みたいのであれば、ライトなものがおすすめです。
チャーミングな味わいで、気取らず飲める赤ワインを選びましょう。
お家で簡単手作り!カッテージチーズの作り方
実はカッテージチーズはお家でも簡単に作れます。
正確にはカッテージチーズ風であって、カッテージチーズの作り方とは異なるのですが、まったく遜色はありません。
材料はすべてスーパーで購入できますし、調理器具も普通のご家庭にあるもので十分です。
では、紹介します。
〈材料〉
| ・牛乳 1000ml ・酢(もしくはレモン汁) 大さじ4杯 ・塩 好みの量 |
たったこれだけです。
これでおよそ300~400gのカッテージチーズを作れます。
〈作り方〉
| ①鍋に牛乳を入れて、かき混ぜながら約60℃に温めます。このとき、牛乳を煮立たせないように気をつけましょう。 ②火を消してから、酢(レモン汁)を入れて、素早く牛乳をかき混ぜた後に静置します。しばらくすると、固形分と水分とに分離します。 ③ボウルの上にザルを置き、ザルの上にキッチンペーパーを敷いて、そこに②を注ぎます。ここで、好みで塩を加えます。固形分から水分が抜け切ったら、出来上がりです。 |
<上手に作るポイント>
| ・固まりにくくなりますので、牛乳を温める際の温度を守りましょう ・レモン汁を使ったほうが、きめ細かな仕上がりになります ※分離後の薄黄色の液がホエイです。栄養が豊富なので、捨てずにスープにするなどをして活用しましょう。 |
カッテージチーズの保存方法
カッテージチーズも他のチーズ同様、冷蔵庫で保存することが望ましいです。
匂いが移ったりしないよう、プラスチックケースのフタをしっかり閉めて保存してください。
開封前であれば、パッケージに記載されている賞味期限内は問題なく食べられますが、一旦開封したら賞味期限は参考にならないため、2、3日以内に食べ切るようにしましょう。
手作りのカッテージチーズは、タッパーなどの密封できる容器に入れて冷蔵庫に入れてください。
ただし、市販のものと比べて傷みやすいため、早めに食べるようにしましょう。
冷凍すると長く保存することができますが、解凍後は食感などが変わりますので、冷凍したまま加熱調理するようにしてください。
まとめ
今回は、チーズの中で最もヘルシーとされる、カッテージチーズについてお伝えしてきました。
シンプルな作り方で若々しい味わいのフレッシュチーズであり、低カロリー・低糖質・低脂肪でありながら、必要な栄養素は豊富に含んでいて、ダイエットにもピッタリでした。
クセのない味わいなので、食べ方もいろいろできて、そのままでも料理に使っても楽しめます。
シンプルな作り方なので、お家でも簡単に手作りできます。
ただし、新鮮さが命のチーズのため、早めに食べ切るように注意も必要でした。
存在は知っていてもあまり馴染みがなかったのが、このカッテージチーズではないでしょうか。
これを機会に、より深くお付き合いをしてみてください。