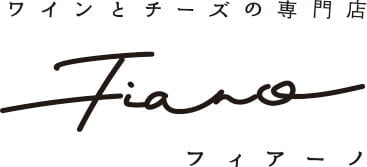「酒は百薬の長」という言葉があります。
しかし実際は、薬の面だけでなく毒の面をのぞかせることがあることも、あなたはご存知でしょう。
それは、お酒の中では健康効果が高いといわれる、赤ワインでも同様です。
やはり、飲むことによるデメリットも存在します。
そこで今回は、赤ワインについて
・どんなデメリットがあるのか?
・メリットには何があるのか?
・赤ワインが健康に良いといわれる根拠は?
・赤ワインの効果的な飲み方は?
などをお話ししてまいりましょう。
「なんとなく体に良さそうだな」と思っていたであろう赤ワインの、メリット・デメリットをまるっと理解できますよ。 もちろん、より健康的に楽しめるようにもなりますので、ぜひ最後までお読みください。

赤ワインにはデメリットがある?

健康に良いとされる赤ワインにも、残念ながらデメリットがあります。
ただし多くの場合は、赤ワインそのものというよりも、飲み過ぎによるデメリット、またはアルコール全般にいえるデメリットです。
「赤ワインならば健康に良い」という話ばかりが独り歩きをしている感がありますので、赤ワインであってもアルコール飲料である以上は、このようなデメリットがあるということを認識しておいてください。
それでは、詳しく見ていきましょう。
肝臓に負担がかかる
赤ワインに限らずお酒を飲むこと自体が、いくつかの臓器に負担をかける点はデメリットといえるでしょう。
特に肝臓は、アルコールを原因とする疾病が発生しやすい臓器です。
胃や小腸で吸収されたアルコールは、肝臓に送られて分解されます。
体内の有害物質の解毒を一手に引き受けて常に働き続けている肝臓に、さらにアルコールの分解をさせるのは大きな負担となっています。
肌荒れにつながる
赤ワインには、肌荒れを引き起こすというデメリットもあります。
肝臓がアルコールを分解するとき、体内の活性酸素が増加するといわれています。
活性酸素は皮膚の細胞も酸化させることで傷つけ、肌荒れやシミ、しわなどの原因となるのです。
他にも、栄養を貯蔵する肝臓がアルコールの分解に力を割かれ、機能が弱まることで体に栄養が行き渡りにくくなり、皮膚の健康が損なわれて肌荒れの原因となるようです。
依存性がある
これも、赤ワインだからというデメリットではないのですが、お酒を日々飲み続けていると、アルコール依存症の危険性が高まります。
アルコール依存症というと、ウイスキーや焼酎などのアルコール度数が高い蒸留酒が原因のように思うかもしれませんが、そればかりではありません。
赤ワインであっても、適量を越えて飲み続けているとリスクは高くなります。
飲み続けることでアルコールに強くなり、飲酒量が増えていきますので、健康被害も発生しやすくなります。
太りやすい

実は赤ワイン自体にはそれほどの糖分はなく、100mlあたり1.5g程度であり、100mlあたり4.9gの日本酒や3.1gのビール、2.0gの白ワインなどと比べると太りにくそうに感じます。
たしかに、赤ワインを飲むだけならあまり気にする必要はないでしょう。
しかし、赤ワインを飲むときは、脂質の多い肉類やチーズを合わせて食べることが多く、食べ過ぎることで肥満につながりやすくなります。
おいしいからというだけでなく、酔うことで食欲が増しますので、適量を超える飲食をしてしまうのも赤ワインのデメリットです。
酒類別糖分量
| 酒類 | 100mlあたり糖分量(g) |
| 赤ワイン | 1.5 |
| 白ワイン | 2.0 |
| 清酒 日本酒 | 4.9 |
| ビール 淡色 | 3.1 |
| 連続式蒸留焼酎 | 0 |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
頭が痛くなる

白ワインでは平気だけど赤ワインを飲むと頭痛になるという人がいます。
原因としては、「アセトアルデヒド」や「亜硫酸塩」「チラミン」「ヒスタミン」などが挙げられていますが、これらは赤ワインだけに含まれるものではありません。
ですから、皆に起こるわけではないのですが、特定の人には発生するデメリットとお考えいただくのがよいでしょう。
赤ワインと頭痛について、詳しくはこちらをご覧ください。

赤ワインのメリットは?
まず赤ワインのデメリットをお伝えしましたが、必ずしも「赤ワインだから良くない」というわけではないのがご理解いただけたでしょう。
やはり、おいしいからと飲み過ぎたり、食べ過ぎたりすることが原因といえます。
逆にメリットには、「赤ワインだからこそ」といえる健康効果がいくつもあります。
続いては、これら赤ワインのメリットについてお話ししましょう。
ただし、飲み過ぎれば、先ほどのデメリットとなることはくれぐれもご注意ください。
老化を予防する

赤ワインが健康に良いといわれる理由の一つに、「ポリフェノール」が含まれていることが挙げられます。
ポリフェノールには抗酸化作用があり、活性酸素を抑制します。
活性酸素とは体内の細胞を酸化させて老化を促進する成分であり、肌にできるシミやしわなども、この活性酸素によることは先述しました。
ですから、赤ワインに含まれるポリフェノールの抗酸化作用は、見た目の老化を防ぐメリットがあるといえるでしょう。
そのポリフェノールのうちの一つである「レスベラトロール」といわれる成分には、さらにこれとは異なる老化の予防効果があることが、近年の研究でわかってきました。
レスベラトロールは、アルツハイマー病の予防やがんの発症リスクを抑えることに働くというのです。
赤ワインには、見た目の老化を防ぐだけでなく、これらの病気のリスクを抑えることで若々しさを保つ効果があるといえるでしょう。
太りにくくなる
先ほどのデメリットで太りやすくなるとお伝えしましたが、それは食事を摂り過ぎてしまうことが原因であり、赤ワインだけを考えれば太りにくくなるというメリットがあります。
というのも、赤ワインに含まれているポリフェノールの一種であるエラグ酸は、脂肪燃焼を促す働きがあるからです。
他にも、ピセアタンノールという物質には脂肪を増やさない、蓄積させないという効果があります。
そもそも赤ワインのカロリーは日本酒などと比べて低く、日本酒が100ml当たり109キロカロリーなのに対して、赤ワインは75キロカロリーです。
カロリーの低いお酒にしたいのであれば、赤ワインは良い選択といえるでしょう。
酒類別カロリー
| 酒類 | 100mlあたりカロリー(キロカロリー) |
| 赤ワイン | 68 |
| 白ワイン | 75 |
| 清酒 日本酒 | 107 |
| ビール 淡色 | 39 |
| 連続式蒸留焼酎 | 203 |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
ワインのカロリーなどについて、詳しくはこちらをご覧ください。
[リンク]ワインに含まれるカロリーは高い?糖質や他のお酒とのカロリーを徹底比較

動脈硬化を予防する
これにも、赤ワインに含まれるポリフェノールが関係しているといわれています。
ポリフェノールは、脂肪の中のいわゆる悪玉コレステロール(LDLコレステロール)が酸化して過酸化脂質になるのを防ぎます。
過酸化脂質は、血管の内側に付着して動脈硬化を引き起こしますので、この生成を抑制できれば動脈硬化は起きにくくなるのです。
また、血管内に過酸化脂質が付着せず血流が良いことで、体温が上がり、痩せやすい体質に変化したり、免疫力が向上したりという効果も見込めます。
血圧を下げる

赤ワインには、カリウムが多く含まれています。
カリウムは、利尿作用を持っているので、体内の塩分を排出することに貢献します。
塩分は高血圧の原因の一つとされていますので、体内の塩分が少なくなれば、血圧も下がるでしょう。
また、先述のレスベラトロールは、血管を柔らかくするというメリットもあります。
血管が柔軟性を失うことも高血圧の原因の一つなので、レスベラトロールの働きによっても高血圧を防げます。
リラックスできる

アルコール自体がリラックスにつながりますが、赤ワインに含まれる芳香成分も私たちの緊張を解きほぐすのに有効です。
赤ワインには多くの芳香成分が含まれていて、単純に良い香りがするだけでなく複雑さも感じられます。
その様々な香りの中から、花や果物、スパイスなどの香りをかぎ分けることで、脳が適度な刺激を受けてリフレッシュにもつながります。
赤ワインが健康に良いといわれる根拠は?
赤ワインを飲むと健康に良いといわれるようになったのには、2つの根拠があります。
1つは赤ワインに特有の効果があるとするもの。
もう1つは、アルコール全般にいえるものです。
これらについて、詳しく見てみましょう。
フレンチパラドックス
欧米人は乳脂肪を多く摂取します。
もちろん国により摂取量が異なっているのですが、各国の乳脂肪の消費量と心臓病の死亡率とが比例するのが一般的です。
しかし、これらの国の中でフランスの比例関係だけが崩れており、脂肪率が飛び抜けて低いのです。
それを受けて、この現象を説明するために、フレンチパラドックスという仮説が提唱されました。
この仮説では、フランス人の赤ワイン消費量が多いことが、ポリフェノールなどの抗酸化物質の多量摂取につながっており、心臓病による死亡率を低くしているとしています。
他の死亡率の低い国を見てみても、ほとんどが1人当たりの年間赤ワイン消費量が多い国なのです。
ただし、この説に関しては、現在では疑問視する説も多くあります。
というのも、確かに赤ワインの飲酒量と死亡率に相関関係は見られるものの、ある実験では赤ワインが原因で心疾患が少なくなるという因果関係は見られなかったからだそうです。
ただ一方では、赤ワインを飲むと抗酸化作用が向上し、血中の過酸化脂質が減少することも実験では証明されているので、完全否定もできません。
ということで確実に言えることは、赤ワインを飲み過ぎればアルコールによる弊害は発生しますので、積極的に赤ワインを大量摂取するのはやめておきましょうということです。
ちなみに、フランス人1人あたりの年間チーズ消費量は、2020年に国際酪農連盟日本国内委員会「世界の酪農状況」が発表したデータでは、27.4kgで世界2位でした。
これは、日本人の2.7kgと比べると約10倍なので、いかに多いかがわかるでしょう。
2020年世界の国民1人当たりチーズ消費量
| 順位 | 酒類 | 国民1人当たりチーズ消費量(kg) |
| 1 | デンマーク | 29.2 |
| 2 | フランス | 27.4 |
| 3 | キプロス | 26.3 |
| 4 | オランダ | 26.0 |
| 5 | フィンランド | 25.4 |
| …… | 日本 | 2.7 |
参考:一般社団法人 Jミルク提供 国際酪農連盟日本国内委員会(JIDF)「世界の酪農状況」
https://www.j-milk.jp/gyokai/database/jidf_faostat.html
J(ジェイ)カーブ
ここまでで、いくら健康によいとされる赤ワインでも飲み過ぎては逆効果だということはおわかりいただけたでしょう。
しかし、適度な飲酒が健康によいというのは、上記のフレンチパラドックスだけが根拠となっているのではありません。
ある調査によると、適度な飲酒をしている人は、禁酒をしている人に比べて死亡率が低いというデータが出たのです。
もちろん、適量を超えてアルコールを過剰に摂取している人の死亡率は、飲酒量に応じて高くなっていきます。
その推移を表すグラフがアルファベットのJに似たカーブを描くので、Jカーブと呼ばれるようになりました。
ただし、このJカーブに関しても、ある程度の相関関係は認められるものの、完全に飲酒量との因果関係が証明されているわけではありません。
普段はお酒を飲まない人が、飲酒をすることで健康になるという証拠はありませんので、「少量の飲酒であればそこまで健康に害はないかもしれない」という程度に認識しておきましょう。

効果的な飲み方は?
ここまでお読みいただいて、「赤ワインは健康に良さそうだけど、飲み方に気をつけなければいけないな」とお気づきになっていることでしょう。
そのとおり、赤ワインのデメリットといっても、結局は「お酒の飲み過ぎ」によることがほとんどです。
ということは、飲み方にさえ気をつければ、赤ワインのメリットのほうを多く受けられるということです。
ここでは、健康に効果的な赤ワインの飲み方について説明します。
適量に抑える
飲み過ぎが良くないことはわかりましたが、適量とはどれくらいなのでしょうか?
厚生労働省が「アルコール」という文書で示している指針では、日本人男性の適量は、純アルコール量で1日当たり10~19gとしています。
ということは、純アルコール量で20gを越えないようにしなければなりません。
純アルコール量20gは、アルコール度数13度の赤ワインであれば約150mlです。
ボトルワインの1/5であり、100ml入りのグラスワインだと1.5杯分です。
ただし、女性の適量はさらに少なく、9gとなっています。
これは、一般的に女性は男性よりも体が小さく、血液量が少ないためです。
また、胃の酵素の濃度が異なるため、男性よりもアルコールの吸収が早いためともいわれています。
純アルコール量9gとは、先ほどの赤ワインの例では70mlです。
また、この文書では、
・少量の飲酒で顔面紅潮を来す等アルコール代謝能力の低い者では通常の代謝能を有する人よりも少ない量が適当である
・65歳以上の高齢者においては、より少量の飲酒が適当である
という文言も記載されていますので、性別や年齢、体質などを考慮して、適量を見極める必要がありそうです。
参考:厚生労働省「アルコール」
https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b5.html
毎日飲まない
いわゆる休肝日を作るということなのですが、実は、休肝日を作ることに効果があるかどうかはわかっていません。
つまり、1週間で飲む量が同じだとすれば、それを7日に分けて飲むか、5日に分けて飲むかによって、健康にどのような影響があるかは明確になっていないということです。
とはいえ、飲酒において気をつけなければならないのは習慣化であり、毎日飲むのが当たり前になってしまうと、飲み過ぎにもつながりやすくなります。
ですから、飲まない日を作ることで、アルコールとの距離を保てるようにするのがよいでしょう。
ただし、飲まない日を作ったからといって、1日のアルコール摂取量が適量を超えることがないようにしてください。
飲む回数が少なくなっても、適量を超える飲酒は体だけでなく脳へのダメージも多くなります。
健康を考えて、ほどほどの量に抑えておきましょう。
食事と一緒に楽しむ
空腹で赤ワインを飲むと、胃からのアルコール吸収が急激に行われ、血中アルコール濃度が一気に高まります。
すると、肝臓をはじめとする臓器への負担が大きくなりますので、食事に合わせてゆっくりと赤ワインを楽しむとよいでしょう。
また、赤ワインは胃酸の分泌を促し、食事の消化を助ける作用もあります。
お互いのデメリットをメリットにすることができますので、赤ワインは食事と一緒に楽しみましょう。
寝る直前まで飲まない
「寝酒」という言葉があるくらいなので、赤ワインを飲むとよく寝られると思っているかもしれませんね。
しかし、実際は、アルコールは睡眠の質を下げるといわれています。
たしかに寝付きは良くなるのですが、浅い眠りになってしまい、場合によっては途中で目が覚めてしまうかもしれません。
また、寝るために赤ワインを飲むクセがついてしまうと、徐々に飲む量が増えていきます。
というのも、アルコールは習慣化すると飲む量を増やさなければ、前と同じ効果が得られなくなるという性質があるからです。
すると、依存症にもなりやすくなりますので、寝酒にするのはやめておきましょう。
これらを考えると、寝る3時間前までには飲み終わるようにするのがよいようです。
食事と一緒に赤ワインを楽しみ、食事が終わってからは飲まないようにするのがおすすめです。
赤ワインの色にこだわらない
これまでに、赤ワインが健康に良い理由として、ポリフェノールがあることをお話ししてきました。
すると、ポリフェノールとは、赤ワインの色素のことのように思ってしまうかもしれません。
たしかに、赤い色素であるアントシアニンも、赤ワインに含まれるポリフェノールの一つではあるのですが、すべてのポリフェノールが色に関係しているわけではないのです。
ですから、色が濃いワインのほうが健康によいというのは必ずしも当てはまりません。
例えば、ピノ・ノワールという品種のブドウは、カベルネ・ソーヴィニョンやシラーなどの品種と比べれば、ワインの色が薄くなる場合が一般的です。
これは、ピノ・ノワールの果皮が薄く、色素が少ないからです。
果皮が薄いということは、病気にも弱いという性質も持っています。
一方で、ブドウなどの植物がポリフェノールを含むのは、病気に対抗するためという理由があります。
したがって、果皮が薄くて病気にかかりやすいピノ・ノワールは、それに対抗するために、実はかなり多くのポリフェノールを含んでいるのです。
ですから、ピノ・ノワールから作られた赤ワインの色が薄いからといって、ポリフェノールが少なく、健康効果が低いということにはなりません。
もちろん、赤ワインの色の濃さは品種だけが関係するわけではありませんので、「色が濃い=健康にいい、色が薄い=効果が少ない」ではないことだけ、覚えておいてください。
まとめ
今回は、赤ワインのデメリットについてお話ししてまいりました。
健康に良いといわれる赤ワインですが、デメリットもあることがわかっていただけたでしょう。
といっても、赤ワイン自体が悪いというよりは、アルコール自体であったり、飲み過ぎてしまうことであったり、赤ワインと一緒に食べ過ぎたりというのが原因でした。
逆に、メリットに関しては赤ワインだからというものが、多かったですね。
ただし、赤ワインが健康に良いというデータはあるものの、はっきりした因果関係までは証明されていないこともご理解ください。
最後には、赤ワインのデメリットが出にくくなる飲み方をお伝えしました。
百薬の長とか、健康に良いとか言われていても、赤ワインは薬ではありません。
いや、薬であっても、飲み過ぎれば毒となります。 今回ご紹介したデメリットがあなたの身に降りかからないよう、上手に赤ワインとお付き合いしてください。