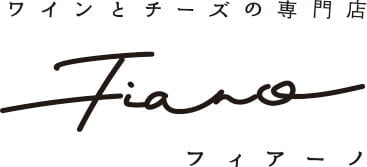「赤ワインは健康にいい!」
多くの人にこのように認識され、赤ワインは“健康に効能のあるヘルシーな飲み物”として、長らく注目を集め続けています。
あなたも、赤ワインから連想する言葉として「ポリフェノール」や「抗酸化作用」などの、健康に関する言葉を思い浮かべるのではないでしょうか。
では、赤ワインの効果効能にはどんなものがあるのかご存知ですか?
今回は、
・フレンチパラドックスについて
・赤ワインの効能と効果がある成分
・赤ワインの健康以外の効能
・飲んで体にいい適量
など、赤ワインの効果効能を軸として、様々な内容をお伝えします。 おいしさだけでなく体が喜んでいることも感じながら、赤ワインを飲めるようになりますので、ぜひ最後までお付き合いください。

赤ワインの効能を世に広めた「フレンチパラドックス」とは?

欧米諸国では、住民が摂取する乳脂肪の量は国によって異なるものの、その量と冠動脈性心臓病での死亡率とは、おおむね一致しています。
ところがフランスでは、この乳脂肪の摂取量が多いにもかかわらず、心臓病での死亡率が低いという奇妙な格差がありました。
この現象を説明するために、唱えられた仮説がフレンチ・パラドックスです。
フランス人は、世界的に見ても赤ワインを多く飲みます。
フレンチパラドックスでは、このことがフランス人の心臓病での死亡率を引き下げているというのです。
いったい、どういうことなのでしょうか?
赤ワインにはポリフェノールという抗酸化物質が多く含まれています。
ポリフェノールは、植物に含まれる抗酸化物質の一種で、植物が紫外線や病害虫から自らを守るために生産します。
ポリフェノールには様々な種類があり、赤ワインに含まれている代表的なものは、赤い色素の「アントシアニン」や渋み成分の「タンニン」などです。
近年では、健康などに多くの効能がある「レスベラトロール」も注目されています。
ポリフェノールは「抗酸化作用」を持っており、細胞を傷つけ、健康を害する「活性酸素」を抑制する働きをします。
つまり、赤ワインに多く含まれているポリフェノールが持つ抗酸化作用により動脈硬化が抑えられ、冠動脈疾患による死亡者が抑えられているというのが、フレンチパラドックスの言いたいことです。
たしかに、フランス以外でも心疾患による死亡率が低い国の多くは、一人当たりの年間赤ワイン消費量が多いというデータがあります。
つまり、赤ワインの消費量と心疾患による死亡率との間には、相関関係があることが実証されています。
そのため、フレンチパラドックスは仮説の域を超えて、事実として扱われ、多くの国に広まりました。
そしてここ日本でも、健康効果を得るために赤ワインブームがやってきたのです。
赤ワインの具体的な効能と効果のある成分

赤ワインから得られる健康に関する効能が広く取り上げられる原因となった、フレンチパラドックスについて紹介しました。
しかし赤ワインの効能は、フレンチパラドックスで注目された、心臓病による死亡率を抑えることだけではありません。
以下で、代表的な効能を紹介します。
動脈硬化を予防する
フレンチパラドックスのところでもご紹介しましたとおり、赤ワイン中のポリフェノールが持つ効果の中で最も知られたものです。
私たちの血液中には、善玉コレステロールと悪玉コレステロールが存在していることはご存知でしょう。
この2種類のうち、悪玉コレステロールが活性酸素により酸化すると血管内部に付着し、動脈硬化の原因となります。
ポリフェノールには抗酸化作用があり、活性酸素を抑制するので、悪玉コレステロールの酸化を防ぎ、動脈硬化を予防できるのです。
血圧を下げる

赤ワインに含まれるカリウムには利尿作用があり、尿と一緒に塩分を体外へと排出する働きがあります。
通常、体内の塩分が多いことは、血圧を上昇させる原因の一つとされています。
ですから、カリウムを含む赤ワインを飲むことは、体内の塩分濃度を低くし、血圧を下げる効果があるのです。
さらに、ポリフェノールの一種であるレスベラトロールには、血管を柔らかくする効果があることで知られています。
血管が硬くなることも高血圧の原因とされますので、ポリフェノールの働きによっても血圧を下げることが期待できます。
老化を予防する

ポリフェノールには抗酸化作用があり、活性酸素が悪玉コレステロールを酸化させるのを防ぐとお伝えしました。
実は、細胞を傷つける活性酸素には老化を早める作用もあるため、ポリフェノールの抗酸化作用で活性酸素を除去することは、老化の予防にも効果があるのです。
研究により、前出のレスベラトロールが、特に強力なアンチエイジング(若返り)効果を持つことも明らかになりました。
レスベラトロールは、アルツハイマー病、がん、その他の老化関連疾患の発症リスクの低下と関連しており、赤ワインは若返りを目指す人々にとっても貴重な効能を持つとされています。
胃腸を守る

赤ワインには多くの有機酸が含まれており、これらが胃腸を守ります。
まずは、これらの有機酸は食欲を増進させたり、消化を助けたりする働きがありますので、あまり食事が進まないときなどに効果があるでしょう。
また、有機酸には殺菌効果も認められてますので、細菌を原因とする食中毒になりにくくすることも可能です。
さらに、胃かいようの原因となる「ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)」の増殖を抑制する効果があるともいいます。
これらの効能は、胃腸に不安を抱えていたり、胃腸を健康に保ちたいと思っていたりする人にはありがたいものといえるでしょう。
うつ症状を予防する

適量の赤ワインを飲むことは、気分の落ち込みを防ぐのに役立つといいます。
科学的研究により、毎週2~7杯のワインを飲む人は、飲まない人に比べて、うつ病の発症率が32%減少することが実証されました。
これは、飲酒により、脳内物質の「ドーパミン」や「セロトニン」が分泌されるためです。
ドーパミンには気持ちを高揚させる働きが、セロトニンには気持ちを落ち着かせる働きがあります。
これらに、赤ワインが持つ香りの良さなどが加わり、リラックス状態へと導き、うつ症状を予防するといわれています。
ただし、リラックス効果を得るために常に赤ワインを飲むようになると、アルコールに依存することになりかねません。
ですから、飲まない日を作るなど適度な距離を保ちましょう。
糖尿病のリスクを低減させる

赤ワインのポリフェノールが、2型糖尿病のリスクを低減させるという研究結果もあります。
ここでもレスベラトロールが、2型糖尿病の発症を減らしている可能性がある成分だと指摘されています。
インスリン感受性を向上させることで、血糖値を減少させる働きをしているのではないかとのことです。
他にも、赤ワインに含まれるミネラルの一つである「クロム」も、血糖値を低下させるインスリンの働きを助けるので、高血糖の管理や糖尿病のリスク抑制に役立つことが期待されています。
赤ワインの美容への効能

赤ワインに多くの健康効果があることはおわかりいただけたかと思いますが、赤ワインには美容への効能もあります。
代表的なものを以下でご紹介します。
ダイエット効果がある
そもそも、赤ワインを飲むと太るのではないかという疑問があるかもしれません。
実は、赤ワインに含まれている糖質はとても低いのです。
日本酒100mlに4.9gの糖質が含まれるのに対して、赤ワインに含まれるのはわずか1.5gです。
白ワインで2.0g、ロゼワインで4.0gなので、これらと比べて少ないのがわかるでしょう。
ウイスキーや焼酎などの蒸留酒が全く糖質を含まないのと比べれば、多いと感じるかもしれませんが、梅酒といった甘いお酒やご飯、パンなどと比較すればとても少なくなっています。
ですから大量に飲まなければ、赤ワインを飲むことによって太ることを気にする必要はないでしょう。
糖質だけでなく、カロリーも気になるかもしれません。
他のお酒や食品と比べて糖質ほどの差は感じないかもしれせんが、カロリーに関しても十分に低いといえるでしょう。
赤ワイン100mlの68キロカロリーは、ご飯100g(お茶碗約2/3杯分)の156キロカロリーと比較すれば、半分以下です。
さらに、赤ワインに含まれるポリフェノールの一種であるエラグ酸には、脂肪の燃焼を促進する効果があるといわれています。
同じく、ピセアタンノールには、脂肪の増加や蓄積を妨げる働きがあるといわれているのです。
これらの働きも考えると、赤ワインはダイエットに効果的といえるでしょう。
食品100g(ml)中の糖質・カロリー
| 食品 | 糖質(≒炭水化物)(g) | カロリー(キロカロリー) |
| 赤ワイン | 1.5 | 68 |
| 白ワイン | 2.0 | 75 |
| ロゼワイン | 4.0 | 71 |
| 日本酒 普通酒 | 4.9 | 107 |
| ビール 淡色 | 3.1 | 39 |
| 連続式蒸留焼酎 | 0 | 203 |
| ウイスキー | 0 | 234 |
| 梅酒 | 20.7 | 155 |
| ご飯 | 37.1 | 156 |
| 食パン | 46.4 | 248 |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
ワインのカロリーと糖質について、詳しくはこちらをご覧ください。

むくみを防ぐ

先ほど、血圧を下げるのにカリウムの利尿作用が効果を発揮するとお伝えしました。
このカリウムの利尿作用は、むくみを防ぐ効能も持っています。
というのも、むくみの原因もまた塩分だからです。
体内の塩分濃度が高まるとこれを一定水準まで下げるために、体は水分を溜め込もうとします。
そのため、むくみが起こるのです。
こうして、水分が排出されなくなることで現れたむくみを、赤ワインのカリウムが塩分の排出を促進することで解消してくれます。
シミ・ソバカス予防ができる
赤ワインに含まれるポリフェノールの抗酸化作用は、活性酸素が肌の細胞を傷つけるのも防ぎます。
肌の細胞が傷ついたことで起こることには、肌のシミやソバカスがあります。
ですから、赤ワインを飲んでポリフェノールを摂取すれば、シミやソバカスの予防も可能です。
赤ワインにはこのように、肌のダメージを防ぐという、美容上の効能も期待できます。
赤ワインの効果を最大限にするための適量とは?

赤ワインには多くの健康効果が期待できますが、飲む量を適量に抑えることが必要です。
また、適量以外にも飲む際には注意していただきたいことがありますので、それらをお伝えします。
赤ワインの適量
赤ワインに限らず、お酒の飲み過ぎが健康に良くないことはおわかりかと思いますが、どの程度の量なら適切だといえるのでしょうか?
厚生労働省は、日本人男性では1日当たり純アルコール10~19g、女性では1日当たり9gまでで最も死亡率が低く、1日当たりアルコール量が増加するにしたがって死亡率が上昇することを提示しています。
つまり、通常のアルコール代謝能力を持つ人であれば、男性なら20g、女性なら10gまでが「節度ある適度な飲酒」量ということです。
女性がより少なく抑えなければならないのは、一般的に男性と比べて体格が小さく、血液量が少ないからであることと、胃液中の酵素の濃度が低いために男性よりもアルコールを吸収しやすいからであるとされています。
アルコール度数13度の赤ワインを150ml飲むと、約20gの純アルコールを摂取することとなります。
1杯を100mlとすればグラス1.5杯分、またはボトルの5分の1が男性の適量で、その半分が女性の適量です。
また、65歳以上の人や、少量のアルコールを摂取しただけで顔が赤くなるような人などもアルコール量を控えることが望ましいとされています。
以上のことから、性別、年齢、体質などを考慮した上で、正確な数値を算出するようにしてください。

休肝日
お酒を飲まない日、いわゆる「休肝日」を設ける必要があるかについては、何らかのメリットをもたらすという明確な根拠はないといわれています。
つまり、同じ量のお酒を飲むのであれば、それを週のうち7日に分けて飲むか、4日に分けて飲むかで、健康に与える影響に差があるとはいえないのです。
とはいえアルコールの習慣化には注意が必要で、毎日飲むことが常態化すると飲酒量は増えていってしまうものです。
飲酒量が増えていけば、当然体へのダメージも大きくなっていきます。
ですから、お酒を控える日を設けることは、お酒との一定の距離を保つことにつながり、良いことといえるでしょう。
ただし、たとえ休肝日を設けても、1日のアルコール摂取量を多くしては、健康への効果が損なわれます。
推奨量以上の飲酒は、体や脳へのリスクが高くなりますので、健康に留意し、適度な飲酒を心がけてください。
夜遅くの飲酒

赤ワインを寝る前に飲めば、ぐっすり眠れるのではないかと思いますよね。
しかし、夜遅くに飲むのは、あまり良い考えではないかもしれません。
というのも、アルコールの摂取は睡眠の質を低下させることが確認されているからです。
たしかに、酔うと早く眠れるということはあるでしょう。
ただし、酔った状態での睡眠は浅くなりがちで、夜中に目が覚めてしまうこともしばしばです。
また、酔いの力で入眠することがクセになるのも危険で、次第に寝つきが悪くなり、より多くのアルコールを必要とするようになります。
ですから、赤ワインを睡眠導入剤の代わりにするような飲み方や、夜遅くに飲むことは避けるのがよいでしょう。
まとめ
現在の日本で、赤ワインは多くの効能が期待できる健康飲料として人気を集めています。
この発端となったのがフレンチパラドックスであり、この説が広まり、今に至っています。
赤ワインの効能に最も貢献しているといえるのが、ポリフェノールによる抗酸化作用です。
動脈硬化をはじめとする様々な健康被害を低減させ、さらにダイエットや肌の若返りに役立つ可能性まであることが明らかにされています。
しかし赤ワインは、適量を守るなど、飲み方に注意しなければ逆効果となってしまいます。
赤ワインを飲む場合は、多くとも男性なら1日グラス2杯、女性なら1日グラス1杯を上限としましょう。 いつまでも健康でいられて、おいしい赤ワインを楽しめるよう、今回お届けした情報を活用してください。