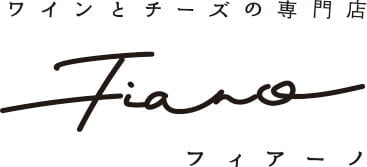チーズが大好きな人もそうでない人も、チーズが動物の乳から作られる発酵食品である事はご存知ですよね。
チーズは発酵食品の中でも種類が多く、全く熟成させないものもあれば、長期にわたって熟成させるものもあります。 今回は、チーズの語る上で外すことのできない「熟成」ついてご紹介します。
熟成のメカニズム

チーズづくりの最後の工程である「熟成」はチーズが元々持っている酵素によって、タンパク質などが分解され、
旨味や風味が増していく工程を指します。
フランスでは、チーズづくりを行う職人を「フロマジェ」、チーズの熟成を専門に行う職人を「アフィヌール」と呼びます。
「フロマジェ」も「アフィヌール」も特に資格の無い職業で、一般的には酪農やチーズづくりに携わる人が長年経験を積み、
技術を習得して職人となります。
日本ではあまり聞かない職業ですが、チーズの種類が最も多いと言われているフランスでは、
2000年にM.O.F.(Meilleur Ouvrier de France) 国家最優秀職人章というコンクールで、「チーズ熟成士部門」が新たにつくられ、
「熟成士」という職業が世間から広く注目されるようになりました。
それほどに重要視されているチーズの「熟成」ですが、 その重要性をご紹介する前に、チーズがたどる熟成までの道のりをご紹介します。
タイプによって違いはありますが、チーズのつくり方を大まかに説明すると以下のような工程になります。
チーズの製造工程
1.温めた原料乳に乳酸菌を加え乳酸発酵させる
人肌くらいに温めた原料乳に乳酸菌を加え、乳酸発酵をさせた後に「レンネット」と呼ばれる凝乳酵素を加えます。
乳酸菌と酵素の働きによって原料乳は豆腐状に固まります。
2.固まった原料乳をカットし水分を抜く
豆腐状に固まった原料乳を「カード」と呼び、抜け出した水分を「ホエー」と呼びます。
カードはカットする大きさによって水分の出かたが変わり、細かくカットすればするほど、ホエーの排出量は多くなります。
目指すチーズの柔らかさに合わせたカットの大きさにします。
3.型詰めと形成
水分を抜いたカードを型に詰め形成します。
4. 加塩
形成されたカードに味付けをします。
塩水に漬けたり、表面に塩を刷り込んだりするなどして、チーズに塩味をつけていきます。
5.熟成
熟成庫に入れ一定期間熟成します。
「発酵」とは、微生物の働きで物質が分解されることを指します。
チーズで言うと、原料乳に加えられた乳酸菌が、乳の持つ糖を乳酸に分解する工程が発酵です。
最後の工程である「熟成」はチーズが元々持っている酵素によって、タンパク質などが分解され、 アミノ酸にかわることで旨味や風味が増していく事を指します。
熟成はチーズの「個性」を生み出す大切な工程

熟成士は生産者からチーズを買い、自身が持つ熟成庫の中で熟成させます。
チーズの種類によって、適した温度・湿度が異なり、目指す味わいや質感によって熟成の環境を調整することが熟成士の仕事です。
「フロマジェ」と「アフィヌール」をどちらも行う職人もいます。
チーズの熟成庫では、温度と湿度をチェックし、ひっくり返したり、棚を移動させたりと ひとつひとつのチーズの状態を確認しながら絶えず熟成を見守ります。
この細かな管理が、チーズの風味「人格」を形成するのだそうです。
熟成の期間と温度

チーズは発酵食品の中でも種類が多く、全く熟成させないものもあれば、長期にわたって熟成させるものもあります。
大まかな、熟成時の温度・熟成期間をタイプ別にご紹介します。
チーズのタイプで熟成期間は変わる
・フレッシュタイプ
水分が多く柔らかいため、基本的に熟成はさせず、出来たてを食べるチーズです。
鮮度が大切なチーズですので、食べる前の他のチーズと同様に10度以下での保存がおすすめです。
・白カビタイプ・ウォッシュタイプ
12度〜14度程度の熟成庫で熟成され、製造後、4週間から8週間程度で食べごろとなります。
白カビチーズの代名詞である「カマンベール・ド・ノルマンディー」の最低熟成期間は21日間。
熟成が進みすぎるとアンモニア臭が出てくることがあります。
・シェーブルタイプ
12度〜14度程度の温度で熟成されます。
最低熟成期間は比較的短く、シェーブルチーズで有名なフランス・ヴァル・ド・ロワール地方の
A O Pチーズの最低熟成期間は10日〜11日間となっています。
・青カビタイプ
8度〜10度程度の熟成庫で熟成されます。
フランスのA O Pに認定されているブルーチーズの最低熟成期間は4週間程度ですが、
おおよそ出荷までに3〜4ヶ月程度熟成させてから出荷されるものが多いです。
・セミハード・ハードタイプ
ハードタイプはその大きさから、熟成の短いものでも4ヶ月〜1年程度熟成させてから出荷されます。
製造時に、チーズの素となる豆腐状の「カード」をカットする際、他のチーズの製造時よりも少し高い温度で撹拌し水分の排出を促します。
熟成時の温度は12度〜18度程度と幅があり、ハードタイプのチーズでは20度程度の温度で熟成される種類のものもあります。
タイプ別 熟成後の変化
驚くほど種類の多いナチュラルチーズ。
同じタイプでも種類によっては全く違う熟成変化を見せるものもあります。
ここでは一般的な熟成変化をご紹介します。
・白カビタイプ
白カビタイプは外側から内側に向かって熟成が進んでいくチーズで、熟成が若いチーズはふわふわとした
白い表皮に覆われており、中身も芯のある少し固い質感です。
熟成が進むと表面の色は次第に赤褐色に変わっていき、内部はトロッととろけた質感に変わっていきます。
ミルクを思わせるフレッシュな香りから、熟成を感じさせる濃厚な香りに変化していきます。
・ウォッシュタイプ
ウォッシュタイプのチーズはその名の通り、塩水やブランデーなどのお酒で表皮を洗いながら熟成させます。
表面の特徴的な色は植物の色素を用いるものもあれば、色素の利用を禁止しているものもあります。
色素の利用を禁止しているものは、微生物が生み出す天然のオレンジ色で、熟成が進むとその色はだんだんと
濃い色合いに変化していきます。
熟成の若いものは、もっちりと弾力があり、熟成が進むとトロリととろけるような質感に変化。
香りはより強くなっていきます。
・シェーブルタイプ
山羊の乳から作られるシェーブルチーズは、ホロホロと崩れやすいことから小型のチーズが多く、様々な形があります。
熟成の若いものは内部が白く、熟成が進むとクリーム色に変化するものが多いです。
表皮の色は、種類によっては木炭の粉がまぶされているものもあるので一概には言えませんが、
熟成が進むと表面を自然のカビが覆い、中身の質感は乾燥して固い食感になるものもあれば、
ほくっとした食感に変化するものもあります。
熟成に関わる微生物の違いによって表面の色に違いがあり、形と同様に様々な熟成変化を楽しめるチーズです。
・青カビタイプ
フランスで初めてA O Pに認定された青カビチーズ「ロックフォール」は、最低90日間の熟成が義務付けられています。
青カビタイプは好気性チーズと呼ばれ、空気に触れさせることで青カビ繁殖することから、最低2週間は洞窟の中で裸のまま熟成させます。
他のブルーチーズも同様に、青カビの生育のためにチーズに空気穴が開けられているものが多く、熟成の進んだものは若いものに比べて少し水分が抜けた印象の質感になります。
全体的に塩味が強いことも特徴のひとつです。
・ハードタイプ
ハードタイプのチーズは大型のものが多く、大きいチーズは水分が少なく、熟成期間も長くなる傾向にあります。
フランスで最大の生産量を誇るA O Pチーズの「コンテ」の熟成期間は4ヶ月から36ヶ月以上のものまであり、イタリアの有名な大型チーズ「パルミジャーノ・レッジャーノ」も同様に長期にわたって熟成をします。
熟成が進むと、ナッツのような芳香と、アミノ酸が結晶化したジャリっとした食感を楽しむことができます。
自宅の冷蔵庫でも熟成はできる?

ハード・セミハードタイプのチーズであれば、購入から数日であればさほど変化はありませんが、ソフトタイプのチーズであれば、日にちが経つにつれて熟成が進むため、好みの食べごろになるまで自宅で熟成させるという楽しみ方もあります。
自宅でチーズを熟成させる際のポイント
- 乾燥しないようチーズ用の包装材、またはラップに包み冷蔵庫で保管する。
- 他の食品の香りが移らないようラップをかけ、さらに保存容器に入れて保存。
- カットされた後のチーズは熟成変化をしないので、早めに食べ切る。
ホールの状態で購入した場合は、包装材の上からチーズを触ってみて、少し硬いと感じるようならば数日待ってみると良いでしょう。
熟成が進みすぎてしまうと、香りが強くなり、後味に強いえぐみを感じる場合があるので、食べる前に表皮や切り口の色合いがキレイかどうか、味見をして後味にえぐみなどを感じないかを確認するようにしましょう。
チーズショップには、今が食べごろのチーズが並んでいるので、自宅で熟成させたい時は、購入時にショップスタッフに食べごろを確認しておくことも大切です。
まとめ
チーズの「熟成」についてご紹介しました。
チーズのタイプによって食べごろの時期は違いますが、共通していることは、クセのない味わいを楽しむのであれば若いタイミングで食べるのが良いというところです。
熟成の進んだチーズは、香りや味の特徴をより強く感じられますが、中には熟成が進みすぎるとアンモニア臭などが出てきてしまうチーズもあるので、購入時にプロであるショップスタッフに相談しておくと良いでしょう。
生産・熟成地域、熟成期間によって同じチーズとは思えないほどの多様な変化を見せてくれるチーズ。 チーズが辿ってきた「熟成」という歴史を感じながら食べると、より一層美味しく感じられますね。