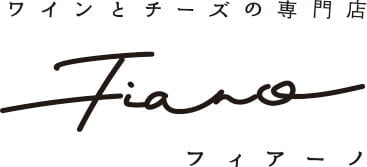お酒の中でも、特に女性に人気の高いのがワイン。
フルーティーな香りと味わいや見た目の美しさ、オシャレさ、種類の多さなど様々な魅力が原因となっているのでしょう。
もちろんそれだけでなく、健康効果を期待してという人も多い気がします。
とはいっても、ワインの健康効果をもたらす栄養素が何なのか、今一つピンとこないかもしれません。
そこで今回は、ワインの栄養素についてお話ししてまいりたいと思います。
・ワインにはどんな栄養素があるのか?
・赤ワインと白ワインでは栄養成分にどんな違いがあるのか?
・赤ワインと白ワイン、それぞれにどんな健康効果が期待できるのか?
といった内容を説明します。 これまで「なんとなく健康に効果ありそうだな」とか「赤ワインのほうが効能があるんだっけ」とかいう程度だった、ワインのメリットがより明確になりますので、ぜひ最後までお読みください。
ワインに含まれる栄養素について

ワインはブドウから作られるため、ブドウに由来する有機酸やミネラル、ビタミンなどの栄養素が含まれています。
どのような栄養成分が含まれており、それぞれどのような働きがあるのかを見てみましょう。
赤ワインと白ワインに含まれる各栄養素の量も表にしてありますので、ご覧ください。
ワイン100mlに含まれる栄養素
| 赤ワイン | 白ワイン | |
| カロリー(キロカロリー) | 68 | 75 |
| タンパク質(g) | 0.2 | 0.1 |
| 脂質(g) | Tr | Tr |
| 炭水化物(g) | 1.5 | 2.0 |
| 有機酸(g) | 0.5 | 0.6 |
| カリウム(mg) | 110 | 60 |
| カルシウム(mg) | 7 | 8 |
| マグネシウム(mg) | 9 | 7 |
| 鉄(mg) | 0.4 | 0.3 |
| ビタミンB2(mg) | 0.01 | 0 |
| ナイアシン(mg) | 0.1 | 0.1 |
| ビタミンB6(mg) | 0.03 | 0.02 |
| パントテン酸(mg) | 0.07 | 0.07 |
| ビオチン(μg) | 1.9 | – |
| ビタミンC(mg) | 0 | 0 |
※「Tr」は検出限界値以下、「-」は未測定を表します
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
カロリー

ダイエットをしていると気になるのがカロリーです。
ワインのカロリーは高いのでしょうか?
赤ワイン、白ワインともにカロリーはあるものの、日本酒100mlでは107キロカロリーもありますので、それと比較すると低いといえるでしょう。
しかも、ワインに含まれるカロリーの多くはアルコール由来であり、すぐに熱となって消費されるとされています。
そのため太りにくいので、ダイエット中にも安心のお酒です。
ワインのカロリーについて、詳しくはこちらをご覧ください。

三大栄養素
三大栄養素といえば「タンパク質」「脂質」「糖質」ですが、そのいずれも低い数値となっています。
ということは、体の成長には貢献しないということですが、裏を返せばダイエットに向いているということです。
特にダイエット中によいのが、糖質がほぼ含まれていない点でしょう。
糖質制限によるダイエットをしているなら、ワインは後ろめたさを感じずに飲めるお酒といえます。
有機酸
ワインには、リンゴ酸や酒石酸、クエン酸、乳酸などの有機酸が豊富に含まれています。
これら有機酸は、もともとブドウに含まれているものもあれば、発酵により生じるものもあります。
近年では、クエン酸の健康効果が多く取り上げられていますので、ワインから摂取できるのはうれしいことですね。
ミネラル類
ワインは、ミネラル類も多く含んでいます。
その中でもカリウムに関しては、赤ワインに多く含まれており、その量は他のお酒と比べても突出しています。
カリウムには、血圧を上昇させる原因の一つであるナトリウムを体外に排出する働きがありますので、カリウムを摂取することで血圧を抑制することが可能です。
塩分の多い食事をするときは、ワインを飲むことで健康効果を期待できるということです。
ビタミン類
ワインに含まれる栄養素の代表といえばビタミン、特にビタミンB類がほとんどといえるでしょう。
ビタミンB2やナイアシン、ビタミンB6、パントテン酸、ビオチンは、すべてビタミンB類に含まれます。
ビタミンB類は、体の代謝機能に多くかかわっており、皮膚と髪の健康サポートをしてくれるので、美容にも欠かせません。
ということは、ワインは健康にも美容にも効果があるということです。
ただし、ビタミンCが含まれないことには注意が必要です。
ワインはブドウが原料なので、ビタミンCを多く含んでいそうに感じますが、発酵によりビタミンCは分解されるため、まったく残存していません。
ビタミンCも、健康と美容のどちらにも大切な栄養素なので、ワインを飲むときは他の食品類から摂るようにしてください。
ポリフェノール類

上記の表には表記されていませんが、ポリフェノールもワインに含まれる栄養成分の代表と言ってよいでしょう。
ポリフェノールは抗酸化物質とも呼ばれ、ワインや野菜、果物などの植物性食品に含まれる微量栄養素です。
代表的なものは、タンニンやアントシアニン、カテキン、レスベラトロールといったものです。
ワインの場合は、主に原料となるブドウの皮や種に含まれています。
抗酸化作用とは、動脈硬化やガンといった成人病の原因となる活性酸素を除去するものです。
活性酸素は細胞を傷つけ、肌などの健康も損ないますので、抗酸化作用は見た目のアンチエイジングにも役立ちます。
ポリフェノールには、この抗酸化作用や抗炎症作用といった幅広い健康効果があります。
赤ワインと白ワインの栄養成分の違いは?

まず大きく異なる点は、赤ワインは、白ワインと比べてより多くのポリフェノールを含んでいることです。
というのも、これらのポリフェノールは、ブドウの皮や種に多く含まれているため、果汁を皮や種と一緒に発酵させて作る赤ワインには多く溶けだしているためです。
ただし、白ワインにもポリフェノールは含まれており、あくまでも、赤ワインとの比較で少ないだけだと認識しておいてください。
他にも、量が大きく異なる栄養成分としてカリウムがあります。
赤ワインは白ワインに比べて、2倍近く多くのカリウムを含んでいます。
先述した通り、カリウムにはナトリウムを排出して血圧を下げる効果がありますので、血圧が気になる人は赤ワインを選択するほうがよいでしょう。
そして、赤ワインはビオチンを含むかどうかでも、白ワインの栄養成分と異なっています。
ビオチンはビタミンB7とも呼ばれる、ビタミンB群の一種です。
食べたものをエネルギーに変えるのを助けるとともに、体内で新しいタンパク質や脂肪酸が作られるのを助ける働きがあります。
逆に、白ワインに多く含まれるのが有機酸です。
有機酸がもたらす健康効果も多くありますので、ぜひ確認してください。
赤ワインの健康効果

赤ワインの健康効果を語るときに外せないのが「フレンチパラドックス」です。
フレンチパラドックスとは、飽和脂肪酸を多く含む食事をしているにもかかわらず、フランス人は冠動脈性心疾患の発症率が比較的低いという現象のことです。
飽和脂肪酸を多く含む食事は、一般的に健康に悪い影響を与えるため、この現象は医師や研究者を長年にわたり困惑させてきました。
しかし、フランス人が赤ワインを多く飲むことから、赤ワインに含まれるポリフェノールがこれらの疾患を抑制しているのが、フレンチパラドックスの原因だという結論に落ち着きました。
このフレンチパラドックスから分かるように、赤ワインには心疾患を抑制する効能があるとされています。
健康効果としては、先述のとおり、カリウムが多く含まれているため、ナトリウムの排出を促進し、血圧低下の効果も挙げられます。
さらには、ポリフェノールの中でも、その一つのレスベラトロールには、脳卒中やある種のがんのリスクを低減できる可能性があることが、研究で示唆されています。
ポリフェノールの抗酸化作用には健康効果だけでなく、細胞の老化を防いで美容にも効果があるとされますので、若々しくありたいならばお酒を飲むときは赤ワインにするとよいでしょう。
赤ワインの健康効果について、詳しくはこちらをご覧ください。

白ワインの健康効果

白ワインは赤ワインに比べ抗酸化物質の含有量が少ないため、健康効果が少ないように思われますが、意外にも多くの健康効果が認められています。
白ワインの特徴として、赤ワインと比べて有機酸が多い点があります。
特に酒石酸には血糖値を下げる働きがあり、血糖値が下がるとインスリンが分泌されないので、ダイエットに効果的です。
他にも、有機酸には強い殺菌効果があるといわれています。
よく、生ガキと白ワインの相性がいいといわれますが、これは味の相性だけでなく、食中毒になりにくくすることでも理にかなっているということなのでしょう。
さらに、有機酸には腸内環境を整える働きもあります。
腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌を減らしますので、腸から健康になりたいのなら白ワインがおすすめです。
白ワインの健康効果について、詳しくはこちらをご覧ください。
[リンク]白ワインは太る?痩せる?糖質・カロリーを知り、健康的・効果的にダイエット!

まとめ
ワインは単においしいだけの飲み物ではなく、ビタミンやミネラルなど様々な栄養素が含まれています。
赤ワインと白ワインには、含まれる栄養成分が異なっており、赤ワインには抗酸化物質のポリフェノールが多く含まれ、白ワインには有機酸が多く含まれます。
その結果、それぞれ独自の健康効果があることが理解できたでしょう。
健康上の効能を得るためには、赤ワイン・白ワインそれぞれの特徴を踏まえて飲むと、健康的な生活を送れるでしょう。
ただし、健康に効果があるワインといえども、アルコール飲料である以上は、飲み過ぎは禁物です。 節度をもって楽しんでくださいね。