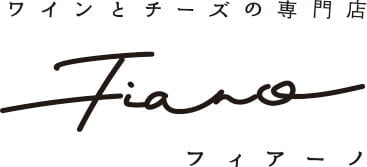「ビールはプリン体が多いから、飲み過ぎないように…」
なんて言葉を、あなたも聞いたことがあるのではないでしょうか。
その時、こう思いませんでしたか?
「じゃあ、ワインのプリン体は少ないの?他のお酒や食材は?そもそもプリン体って何?摂り過ぎるとどうなるの?」と。
たしかに、ワインや他のお酒に含まれるプリン体は、ビールと比較すると多くありません。
しかし、お酒の種類によるプリン体の量の違いだけを気にしていたのでは、病気の原因となるプリン体の摂り過ぎを防ぐのに十分ではないのです。
他にも、プリン体に関しては、多くの人に知られていないのではないかということがいくつかあります。
ということで、今回は耳にする機会が多いわりに、詳しいことは案外知られていないプリン体についてお話しします。
・そもそもプリン体ってどんなものなのか?
・プリン体が多いとなぜよくないのか?
・ワインなどの酒類・食品に含まれるプリン体の量
・プリン体の悪影響を受けないための適量や飲み方
などを取り上げてまいります。 好きなワインを飲み続けていても、プリン体が原因となる病気などを防ぐのに役立つ情報をお届けしますので、ぜひ最後までお付き合いください。

ワインにも含まれるプリン体について

プリン体は、ワインをはじめ多くのお酒や食品に含まれます。
これほど身近なプリン体ですが、プリン体についてどのくらいご存知でしょうか?
まずは、プリン体についての説明からしてまいります。
プリン体とは?
プリン体といえば「ビールや高級食材に多く含まれているもの」というイメージがあるかもしれませんが、実はほとんどの食品やアルコール飲料に含まれる物質であり、私たちが普段口にするワインにも含まれています。
動植物の細胞の核には核酸というものがあり、その核酸の主成分となっているのがこのプリン体です。
一般的には「“うま味”が多いものはプリン体も多い」といわれています。
このプリン体は、ワインなどのお酒や料理から摂取した後、肝臓で分解されて尿酸となり、尿と一緒に排出されます。
しかし、プリン体を摂り過ぎると尿酸が大量に発生し、排出しきれなくなって体内に蓄積されることとなり、それが様々な症状を引き起こすようになるのです。
ちなみに、日本痛風・核酸代謝学会が発表している「高尿酸血症・痛風の治療ガイドライン」では、一日に摂取してよいプリン体の上限は400mgとされているようです。
ただしプリン体は、私たちの体内でも作り出されています。
というより、むしろ体内で作られる割合のほうが多く、全体の7~8割を占めています。
対して、料理やお酒などから摂取されるのは2~3割です。
ですから、ワインなどのプリン体が少ないお酒を選んだとしても、体質などを原因として体内で多く作られることもあるようです。
そうなると、何らかの症状が出ることもあり得ます。
先ほどの400㎎という上限が絶対的なものではありませんので、心配であれば一度検査を受けることをおすすめします。
ワインとプリン体、痛風の関係は?
ワインにもプリン体が含まれると述べましたが、ワインと一緒に体内に取り込まれたプリン体は、肝臓で分解され尿酸になります。
作られた尿酸は、一旦「尿酸プール」と呼ばれるところに溜められ、体内の尿酸量を一定に保つために使われます。
そして、食事などから摂ったプリン体が多くなり、この尿酸プールから尿酸があふれると、尿と一緒に排出されるのです。
しかし、プリン体を摂り過ぎるとさらに尿酸の量が増え、尿酸の排出が間に合わなくなってしまい、血液中の尿酸値が基準以上に高まります。
この症状を「高尿酸血症」と呼びます。
そして、この高尿酸血症の状態が続くと、ある日突然、足の親指の付け根やかかと、足の甲などに激痛が走ることとなるのですが、これが「痛風」と呼ばれる、尿酸の結晶が関節内などに蓄積されて神経を刺激する症状です。
つまり、プリン体を摂り過ぎてしまうと、痛風になる可能性が高いということです。
痛風はその名の通り、風が吹いても痛いというくらいに激しい痛みが患部を襲い、歩くことすらできなくなるといわれていますので、この症状に見舞われた人は二度と同じ痛みを味わいたくないといいます。
ただし、プリン体の摂り過ぎが原因の高尿酸血症が引き起こすのは、痛風だけではありません。
他にも、尿の通り道に尿酸の結晶ができる尿路結晶や、慢性腎臓病、心血管疾患などの原因ともなりますので、いずれにしてもプリン体の摂り過ぎには気をつけてください。
ワインをはじめとする酒類・食品のプリン体含有量は?

ここまで、プリン体について、またプリン体が引き起こす症状などに関してお話ししてまいりました。
ここで、あなたはどんなお酒や食品に、どれくらいのプリン体が含まれているのかと、気になっていることでしょう。
ということで、ワインをはじめとする酒類、私たちに馴染みのある食品に含まれるプリン体の量を見てみましょう。
ワインなど酒類のプリン体含有量
冒頭で述べましたが、お酒の中で多くのプリン体を含んでいるのはビール類であり、ワインにはあまり含まれていません。
気をつけなればならないのは、同じビール類であっても、一般的なビールよりも地ビールのプリン体が多くなっていることです。
また、ワインの中では、一般的に赤ワインのほうが白ワインよりもプリン体が多いとされています。
これはワインの製造方法によるもので、種子や皮も一緒に醸して作る赤ワインではプリン体が多くなるようです。
それと同時に、ブドウの品種によっても含まれるプリン体の量が異なるといわれます。
あと、ワインやビール、日本酒などの醸造酒には多くのプリン体が含まれる傾向にあります。
これは、原料を発酵させることで作られる醸造酒には、多くのエキス分が残るためです。
一方、焼酎やウイスキー、ブランデーなどの蒸留酒にほとんどプリン体が含まれないのは、これらのお酒が醸造酒をベースにして、蒸留というアルコール分だけを取り出すような製法で作られているためです。
もし、お酒を飲みたいけれど、プリン体は少ないほうがいいというのであれば、蒸留酒を選択するのがよいでしょう。
醸造酒を飲みたいというのであれば、ワインにすることをおすすめします。
アルコール飲料中のプリン体含有量
| アルコール飲料(100ml) | 含有量(㎎) |
| ワイン | 0.4 |
| 日本酒 | 1.2 |
| ビール | 3.3~6.9 |
| 発泡酒 | 2.8~3.9 |
| 発泡酒(プリン体カット) | 0.1 |
| 紹興酒 | 11.6 |
| 地ビール | 5.8~16.6 |
| 焼酎25% | 0.0 |
| ウイスキー | 0.1 |
| ブランデー | 0.4 |
| 低アルコールビール | 2.8~13. |
| ビールテイスト飲料 | 1.3 |
| その他の雑酒 | 1.7~2.3 |
出展:公益財団法人 痛風・尿酸財団(編集して記載)
食品のプリン体含有量
では、ワインを飲むことに決めたとしましょう。
そうなれば、やはり何かしら食べるものも欲しくなりますよね。
その際の食事にプリン体が多く含まれていれば、当然プリン体の摂取量は多くなります。
ですから、ワインに含まれるプリン体が少ないからといって安心するのは危険です。
食事から摂取する分も計算して、プリン体の総量を考えるようにしてください。
では、どんな食品にプリン体が多く含まれるのか、それぞれについて見てみましょう。
ここで注意していただきたいことがあります。
一般的に野菜など植物性の食品のプリン体は少ないのですが、干し椎茸には100g中379.5mgのプリン体が含まれています。
乾燥しているせいで、重量に対してのプリン体含有量が多くなっていますので、ご注意ください。
魚類

魚類は全般的に多くのプリン体を含んでいるといってよいでしょう。
ただし、種類による傾向の違いはあり、いわゆる赤身魚のほうが多く含まれており、白身魚には少ないようです。
そして、干物などの乾燥させたものは、プリン体が多くなる傾向にあります。
また、魚卵には多くのプリン体が含まれているといわれることが多いのですが、物によっては、むしろ少ないといえるほどです。
明太子とイクラでは、同じ魚卵といってもプリン体含有量では大きく異なっています。
貝・軟体動物

貝類・軟体動物類も、100g中に含まれるプリン体が100㎎を超えるものばかりです。
いずれも、うま味を多く感じる食品ばかりで、「プリン体=うま味」といわれるのもうなずけるでしょう。
内臓類
魚類・肉類を問わず、身の部分と比べて多くのプリン体を含むのが内臓類です。
特に、レバー(肝臓)は多くのプリン体を含んでいます。
尿酸値を気にしているのであれば、内臓類の食べ過ぎには気をつけてください。
食品中のプリン体含有量
| 食品(100g) | 含有量(㎎) |
| カツオ | 211.4 |
| マグロ | 157.4 |
| マサバ | 122 |
| マイワシ(干物) | 305.7 |
| カツオブシ | 493.3 |
| ニボシ | 746.1 |
| マダイ | 128.9 |
| ヒラメ | 133.4 |
| サケ | 119.4 |
| 明太子 | 159.4 |
| イクラ | 3.7 |
| カズノコ | 21.9 |
| カキ | 184.5 |
| アサリ | 145.5 |
| タコ | 137.3 |
| スルメイカ | 186.8 |
| クルマエビ | 195.3 |
| ズワイガニ | 136.4 |
| 豚レバー | 284.8 |
| 牛ハツ | 185.0 |
| あんこう肝(酒蒸し) | 399.2 |
| イサキ白子 | 305.5 |
出展:公益財団法人 痛風・尿酸財団(編集して記載)
お酒と食品のプリン体の量についての注意点
ここまでのお話しで、お酒と食品の種類を選べば、摂取するプリン体の量を抑えられると考えていることでしょう。
しかし残念ながら、それだけで安心とはいえません。
なぜなら、アルコール自体が尿酸の生成に関与しているからです。
どういうことかといいますと、お酒を飲むとアルコールが体内に吸収されて、肝臓で分解されるのはご存知でしょう。
この分解にはエネルギーが必要で、ATPという物質がエネルギー源として消費されます。
実は、このATPにはプリン体が多く含まれており、ATPのエネルギーを利用した後にはこのプリン体が放出されるのです。
プリン体が分解されて尿酸が生成されるので、プリン体の少ない飲食物を飲んだとしても、別の経路で尿酸が発生してしまいます。
また、アルコールが分解されて生成される乳酸には、腎臓が尿酸を排出するのを阻害する働きがあるため、お酒を飲むにしたがって体内の尿酸の量を減らすことができなくなってしまうことも知っておいてください。
尿酸を排出できないのに、アルコールの利尿作用により体内の水分はどんどん出ていきますので、血液中で尿酸の占める割合は高くなる一方です。
このような理由で、プリン体の摂取を抑えたとしても、尿酸値が上がることも珍しくありません。
事実、痛風を発症する人の多くは、ビール類以外のお酒を飲んで発症しています。
つまり、ビールをはじめとするプリン体を多く含む物を飲食することだけが、痛風を引き起こすわけではないということです。
ですから、尿酸の発生をギリギリまで押さえたいのであれば、お酒類はすべて避けて、ノンアルコール飲料を選ぶのも一つの方法です。
ただし、1日1杯のワインなど適量のアルコール摂取は、アルコールを全く飲まない人に比べて痛風の発症リスクを下げるという研究結果もあるそうです。
この量を守れるのであれば、ワインなどの酒類が痛風のリスクを減らすのに役立つかもしれません。
とはいえ、適量を超える飲酒は、痛風のリスクを確実に高めるといわれていますので、くれぐれも飲み過ぎには気をつけましょう。
尿酸値を上げない、ワインの適量と飲み方

ここまで、ネガティブな内容ばかりとなってしまいました。
しかし、現状で高尿酸血症などの症状が表れていないのならば、適量の飲酒はかまわないでしょう。
ワインならどれくらいの量まで、尿酸値を上げずに済むのか、適量についてお話しします。
また、量だけでなく、飲み方によっても、尿酸値に影響があるといいますので、尿酸値を上げない飲み方についても説明します
尿酸値を上げない、ワインの適量
アルコールが痛風の発症リスクを下げるという研究結果もありますが、先述のとおりアルコール自体によるリスクにも注意が必要です。
先ほど、1日にワインをグラス1杯までなら痛風のリスクを下げられるという、研究結果をお伝えしました。
ですから、尿酸値を上げないという観点からは、1日にグラス1杯のワインを適量と考えてください。
とはいっても、グラス1杯では足りないと思うかもしれませんね。
そんなときは、グラス2杯までなら、許容範囲と考えてよいかもしれません。
これは、成人男性が1日に摂取してよい純アルコール量を20g以下としている、厚生労働省のデータを基準にしています。
純アルコール量20gとは、アルコール度数13%のワインでは150m強となり、100mlのグラスワインで1.5杯です。
以下で紹介する飲み方に気をつければ、2杯までは健康的に飲み続けられる量だと思ってよいでしょう。
ただし、体の小さな女性や高齢者、お酒に弱い人には、この量では多いので、性別や年齢、体質などを考慮して量を調節してください。
参考:厚生労働省「アルコール」
https://www.mhlw.go.jp/www1/topics/kenko21_11/b5.html
尿酸値を上げないワインの飲み方

尿酸値を上げないための適量についてお話ししましたが、飲み方についても注意が必要です。
3点ほどお伝えします。
水をたくさん飲む
ワインに限らず、お酒を飲むときには水を多く飲むことが大事です。
その効果はいろいろありますが、その一つとして尿を多くすることで尿酸を排出させて、体内の尿酸値を上げないようにできることが挙げられます。
悪酔いを防いだり、内臓への負担を軽くしたりと他にもメリットがありますので、ワインを飲むときは水をたくさん飲むよう心がけてください。
プリン体の少ない料理と合わせる
プリン体は食品にも多く含まれており、ワインだけでなく料理のプリン体にも気をつけるようにお伝えしました。
ということは、尿酸値を上げたくなければ、ワインに合わせる料理のプリン体を少なくするほうがよいでしょう。
卵やチーズは、プリン体をほとんど含まない食品なのでおすすめです。
他にも、プリン体の含有量が少ない食品はいろいろありますので、これらをうまく取り入れて、料理からのプリン体摂取量も少なくしてください。
以下で、プリン体の少ない食品を紹介します。
食品中のプリン体含有量(少ないもの)
| 食品(100g) | 含有量(㎎) |
| 鶏卵 | 0.0 |
| うずら卵 | 0.0 |
| 牛乳 | 0.0 |
| チーズ | 5.7 |
| 白米 | 25.9 |
| 小麦粉(薄力粉) | 15.7 |
| もやし | 44.7 |
| そら豆 | 35.5 |
| グリンピース缶詰 | 18.8 |
| なめこ | 28.5 |
| ピーナッツ | 49.1 |
| 豆腐 冷奴 | 31.1 |
出展:公益財団法人 痛風・尿酸財団(編集して記載)
カリウムを含む食品を食べて利尿を促進する

先述のとおり、尿酸は尿と一緒に排出されます。
それであれば、尿を多く出せば尿酸値も下げられるということです。
そこで、利尿作用を持つカリウムが含まれている食品をとるとよいでしょう。
カリウムは、野菜や果物、海藻類などに多く含まれていますので、ワインを飲むときは、これらの食材を使った料理を合わせてください。
ただし、気をつけていただきたいのが、カリウムを摂取して利尿を促すだけでは、逆効果になることです。
体内の水分が少なくなると、血液も凝縮され相対的に尿酸値も上がります。
しっかり水を飲んで、尿として排出された水分を補うようにしてください。
カリウムを多く含む食品中のカリウム含有量
| 食品(100g) | 含有量(㎎) |
| えだ豆 生 | 590 |
| 西洋かぼちゃ 焼き | 570 |
| コリアンダー 葉 生 | 590 |
| ドライトマト | 3200 |
| にんじん 生 | 630 |
| パセリ 葉 生 | 1000 |
| ほうれんそう 葉 生 | 690 |
| あんず 乾 | 1300 |
| いちじく 乾 | 840 |
| 干しがき | 670 |
| 干しぶどう | 740 |
| ドライマンゴー | 1100 |
| さつまいも 蒸し 切干 | 980 |
| さといも 球茎 水煮 | 560 |
| じゃがいも 乾燥マッシュポテト | 1200 |
| いんげんまめ 全粒 乾 | 1400 |
| えんどう 塩豆 | 970 |
| そら豆 全粒 乾 | 1100 |
| いり大豆 | 2000 |
| あおさ 素干し | 3200 |
| あおのり 素干し | 2500 |
| まこんぶ 素干し 乾 | 6100 |
| 乾燥わかめ 素干し | 5200 |
出典:日本食品標準成分表2020年版(八訂)
まとめ
今回は、ワインにも含まれているプリン体のお話をしてまいりました。
プリン体は多くのお酒や食品に含まれていて、摂り過ぎると尿酸値が上がり、それが痛風につながるのでした。
ワインに含まれるプリン体は比較的少ないのですが、酒類、その他の食品類にも、プリン体が多いものから少ないものまで様々あることはご理解いただけたでしょう。
また、ワインにプリン体が少ないからといって、一緒に合わせる料理の食材にプリン体が多ければ、摂り過ぎの危険性があることもお伝えしました。
さらに、ワインと料理でのプリン体の摂取量を抑えたとしても、アルコール自体が尿酸値を上げてしまうことには驚きでした。
これらのことも含め、ワインを1日にグラス1杯程度にしておけば、尿酸値が上がり過ぎる心配はなさそうです。
あとは、水をたくさん飲んだり、野菜類を食べるなどすれば、さらに心配は少なくなるでしょう。
発症した人の誰もが恐れるのが、痛風の痛みです。 痛風やその前段階の高尿酸血症などにならないよう、プリン体の量に気をつけながら、おいしいワインと料理を楽しんでいきましょう。