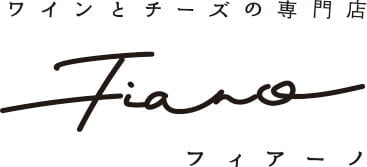乳児の食物アレルギーの原因として、卵に次いで牛乳・乳製品が多いのはご存知でしょうか。
これは、牛乳に含まれるタンパク質の「カゼイン」が原因となり起こります。カゼインは加熱や発酵でもアレルギーを起こす力が落ちないため、牛乳を原料とするチーズやヨーグルトなどを食べても症状が出ます。
アレルギーの症状は、じんましんや喘息をはじめとして様々です。また、軽いものから重いものまであり、時には生命の危険すらあるので、アレルギーの原因となる物質を摂らないよう注意が必要です。
今回はアレルギーの原因となる食品の中でも、牛乳から作られる乳製品、特にチーズに焦点を当てて解説したいと思います。
チーズアレルギーは一般的に子供に多いのですが、大人でも症状が出る場合がありますので、しっかりと知っておいたほうがよいでしょう。
ということで、そもそもアレルギーとは何か、チーズアレルギーの原因や症状とは、チーズアレルギーの人へのチーズの代替食品、といったことをお伝えします。
ご自身や子供さんがチーズアレルギーかもしれない、もしくはチーズアレルギーになったらどうしようとお考えなら、ぜひ最後までお読みください。
なお、アレルギー症状は、場合によっては生命にかかわることがありますので、安易な判断はせず必ず専門医の判断を仰いでください。
また、本記事は一般的な注意喚起を行う目的に限定して執筆しておりますので、詳しくは専門機関が出している情報を参考にしてください。
チーズアレルギーとは

チーズアレルギーとは、チーズを食べることで、心身、特に体に有害な症状が出ることをいいます。
本来は体を守るはずの免疫機能が、チーズに含まれているアレルギーの原因となる物質(アレルゲン)に反応することで発症します。
では、そもそも食物で起こるアレルギーとはどのようなものなのでしょうか。
また、チーズの原料は牛乳であり、この牛乳を飲むとお腹がゴロゴロするという人がいますが、この症状もチーズアレルギーと関係あるのでしょうか。
食物アレルギーについて

食物アレルギーとは、食物に含まれるタンパク質を
・食べる
・触る
・吸い込む
ことで、体の免疫システムが反応して、じんましんや咳が出るなどの症状を引き起こすことです。このアレルギーの原因となる物質を「アレルゲン」と呼びます。
一般的に、乳児期に発症しやすく、年齢と共に症状が出なくなる傾向にあり、原因となる食物も変化していくのが特徴です。
しかし、子供時代に食物アレルギーがなくても、大人になって突然発症する場合もあります。
それは、人がアレルゲンを処理する能力には限界があり、その限界量を超えると症状が出るという性質があるからです。ですから、幾度にもわたりアレルゲンを処理し続けた結果、限界を超えて発症に至ります。
原因となる食物が様々であるだけでなく、症状も異なり、かつ発症までの時間も一定ではありませんので、飲食の後の体調変化の原因が食物アレルギーにある可能性があります。
年齢群別原因食物(粗集計)
| 0歳 (1,876) | 1・2歳 (1,435) | 3-6歳 (1,525) | 7-17歳 (906) | 18歳~ (338) | |
| 1 | 鶏卵 60.6% | 鶏卵 36.3% | 木の実類 27.8% | 牛乳 16.9% | 小麦 22.5% |
| 2 | 牛乳 24.8% | 牛乳 17.6% | 牛乳 16.0% | 木の実類 16.8% | 甲殻類 16.9% |
| 3 | 小麦 10.8% | 木の実類 15.4% | 鶏卵14.7% | 鶏卵 14.5% | 果実類 9.8% |
| 4 | 魚卵 8.2% | 落花生 12.0% | 甲殻類 10.2% | 魚類 7.7% | |
| 5 | 落花生 6.6% | 魚卵 10.3% | 落花生 9.1% | 木の実類 5.9% | |
| 6 | 小麦 5.8% | 小麦 6.7% | 果実類 7.8% | 牛乳 5.0% | |
| 7 | 小麦 7.6% | ||||
| 小計 | 96.2% | 89.8% | 87.5% | 82.8% | 67.8% |
出展:令和3年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業報告書(消費者庁)
乳糖不耐症との違い

チーズを食べて、お腹がゴロゴロしてきたらアレルギーなのでしょうか?
たしかに、アレルギーの可能性もあります。
しかし、はっきりしたことは言えないのですが、その場合は乳糖不耐症かもしれません。
多くのチーズは牛乳から作られますが、牛乳にはお腹がゴロゴロする原因となる物質が含まれています。それが乳糖です。
ですから、この乳糖によりお腹の不調が起こっている可能性があります。
とはいえ、乳糖はチーズを製造する際に固形分と分離される液体の中に多く含まれており、固形分である製品にはほとんど含まれません。
なので、一般的にはチーズでお腹がゴロゴロすることはないのですが、チーズの種類や食べる量、体調などによってまれに症状が出ることがあります。
ですから、ただちにアレルギーだと判断しないほうがよいでしょう。
ただし一般の人には、アレルギーか乳糖不耐症かの判断はできませんので、チーズを食べてお腹の調子が悪くなったのであれば、医療機関に相談してください。
チーズアレルギーの原因
すでに説明したとおり、牛乳はアレルギーの原因となる食品です。そして、多くのチーズが牛乳から作られるため、チーズアレルギーも多くは牛乳が原因となっています。
しかし、チーズアレルギーの原因は牛乳だけではありません。
ここでは、チーズアレルギーの原因についてお話しします。
チーズアレルギーで注意すべき原材料
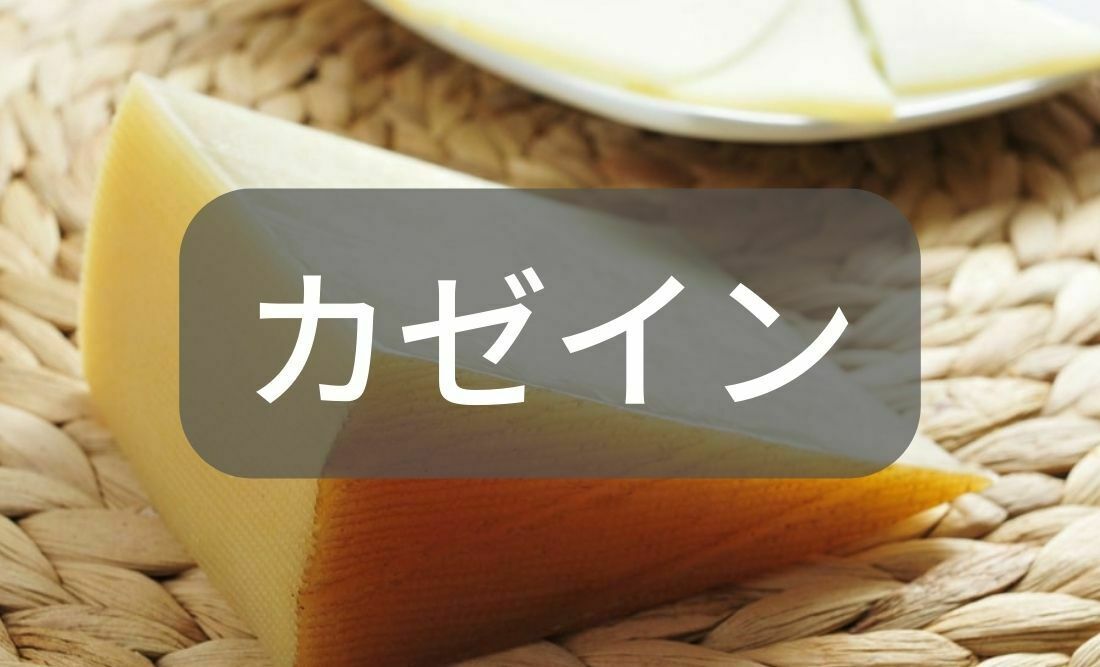
多くのチーズアレルギーは、牛乳に含まれる乳タンパクの「カゼイン」がアレルゲンです。このカゼインは加熱や発酵によって力が弱まりませんので、チーズになってもアレルギーを引き起こします。
では、牛以外の動物の乳が原料となっているチーズではアレルギーは起きないのでしょうか?
残念ながら、ヤギや羊の乳から作られるチーズでも発症の可能性はあります。
ただし、ヤギや羊の乳は食品表示上の義務がないため、アレルギー物質として記載されません。
ですから、ヤギや羊の乳から作られているチーズの包装を見て、アレルギー物質が入っていないと判断しないように気をつけてください。
また、食品表示に「牛乳」や「ヤギ乳」などと記載がなくても、乳由来の原料である「ホエイ」や「カゼイン」「脱脂粉乳」などにもアレルゲンが含まれますので、パッケージに表記されている原材料についてはしっかり確認するようにしましょう。
逆に、「乳」という文字が使われていても、「乳化剤」や「乳酸菌」などにはアレルゲンは含まれませんので、乳製品とは区別してください。
もう一つ気をつけていただきたいのは、外食をする場合です。
容器包装されている加工食品では、これらのアレルギー物質や原材料の表記は義務化されていますが、飲食店で料理として提供する際の表示義務はありません。
ですから、チーズアレルギーの心配がある場合には、「牛乳」などの動物乳だけでなく、チーズやヨーグルト、ホエイといった乳製品や乳加工品のすべてについて、使用していないかを確認するようにしましょう。
また、材料として入っていない場合でも、同じ調理器具を使用するだけで発症する可能性もありますので、器具や容器についても共用していないか質問するようにしてください。
牛乳は大丈夫でもチーズアレルギーは起こる

ここまで、チーズアレルギーの主な原因は、牛乳をはじめとする乳製品全般だとお伝えしました。
それであれば、牛乳を飲んで大丈夫なら、チーズアレルギーは出ないと思われそうですが、実はそうではありません。
牛乳以外が原因となって、起こるチーズアレルギーもありますので、それについて説明します。
カビが原因
世の中には、カビが原因となって起こるアレルギーがあります。
そして、チーズにはカビを利用して製造するものがあります。
ご存知のように、カマンベールやブリーを代表とする「白カビチーズ」と、ロックフォールやゴルゴンゾーラを代表とする「ブルーチーズ」です。
これらは、製品自体にカビが繁殖した状態で販売され、カビも一緒に食べるのが一般的です。
ですから、このカビが原因となってアレルギーが引き起こされることがあります。
もし、カビのチーズでアレルギーが出た場合は、乳とカビのどちらが原因か一般の人には判断できませんので、専門の医師によって原因を明らかにしてもらいましょう。
リゾチームが原因
チーズアレルギーには、卵白に含まれる「リゾチーム」が原因のものもあります。
といいますのも、このリゾチームには殺菌作用があるため、チーズの製造に使用されることもあるからです。
ですから、卵アレルギーがある人がこのようなチーズを食べれば、発症する可能性があります。
ということは、牛乳を飲んでも大丈夫であり、カビのチーズでもないからといっても、チーズアレルギーにならないとは限りません。
アレルギーが心配であれば、原材料の表示に「リゾチーム」の記載がないかしっかり確認してください。
チーズアレルギーの症状

他の食物アレルギーで様々な症状が出るように、チーズアレルギーでも特定の症状が出るわけではありません。
一般的には、その人の最も弱いところに発症すると言われています。
また、症状が出るまでの時間も一定ではありません。
発症時間の違いによる2つのタイプについてお話しします。
即時型アレルギー
一般的にアレルギーだと認識されているものは、食後2時間以内に発症します。このように、比較的早く症状が出るものが、即時型のアレルギーです。
症状は、アレルギーとしては代表的なものであり、鼻が弱い人の場合は鼻炎、皮膚が弱い人ならじんましんという具合に、その人の弱い部位に現れます。
ただし、1か所だけとは限らず複数の症状が出る場合もあります。
これが「アナフィラキシー」です。
特に血圧の低下や意識障害を伴う症状は「アナフィラキシーショック」といいます。この場合は、速やかに治療しなければ死に至ることもありますので、注意しなければなりません。
遅延型アレルギー
即時型に対して、数時間後、遅い場合には数週間後に発症するものを遅延型アレルギーと呼びます。
こちらは、一般的なアレルギー症状に限らず、だるさや頭痛、さらには“うつ”といった、アレルギーとは思えないような症状を引き起こすこともあります。
この場合は、アレルギーという自覚がないばかりか、チーズが原因とも考えられないでしょう。
原因不明のだるさや頭痛、めまいなどがある場合は、遅延型アレルギーの可能性も考えられますので、一度専門医に相談してみてください。
チーズアレルギーの場合の代替食品
もしチーズアレルギーであるならば、チーズをはじめとする乳製品を口にすることは避けるべきです。
しかし、チーズを食生活から除くとなると、味覚の楽しみを一部失うこととなるでしょう。ですから、チーズを食べた気分になるものが欲しくなるはずです。
また、栄養豊富なチーズを食べないとなると、代わる食品で栄養補給をしなければなりません。
ここでは、それら代替食品についてお話しします。
乳を使用しないチーズの代替食品
まずは、乳を使用しないで製造したチーズのような食品を紹介します。
現在では、豆乳やココナッツミルクを原材料にして、チーズのような風味・食感に作られたものがあります。
名前は様々ですが、「チーズアレルギー 代替食品」などと検索をかけると、たくさんの商品がヒットします。
スーパーで販売されているものもあるようですが、そこまで一般的ではないようなので、手に入らなければネットで購入するのがよいでしょう。
チーズの味を求めるならば、ぜひ購入を検討してみてください。
カルシウムを多く含む食品
他にも、チーズを食べられなくて困るのは栄養面で不足することであり、特にカルシウムです。
数ある食品の中でも、チーズはかなり優秀なカルシウム源です。
ただでさえ日本人に不足しがちなカルシウムは、チーズから摂取できなければさらに不足が心配になります。
なので、チーズアレルギーであれば代わりの食品からカルシウムを摂るしかありません。
そこでおすすめなのが、小魚や干しエビ、小松菜などです。特に海産物にはカルシウムが豊富に含まれますので、覚えておいてください。
カルシウムが不足すると、
・骨や歯がもろくなる
・神経系の痙攣症状が出る
・子供の場合、発達障害になる
といったことが起こりやすくなります。
これらを予防するためにも、チーズの代替食品からカルシウムをしっかり摂取しましょう。

まとめ
今回は、チーズアレルギーについてお話ししました。
そもそも、食物を原因とするアレルギーとはどういうものなのか、チーズアレルギーはなぜ起こるのかといったことをお伝えし、どのような症状が出るのかを説明しました。
また、チーズに代わる食品についてもお分かりいただけたでしょう。
大人でも、突然発症する恐れがあるのがチーズアレルギーです。
知識を深めて、いざというときに備えてください。