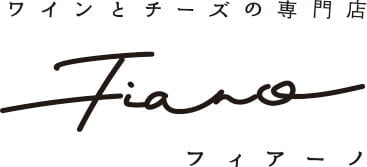「ワインは料理と合わせてこそ、本来のおいしさを発揮する。」
これは、ワイン愛好家だけでなく、普段あまりワインを飲まない人たちにも浸透している考えです。ですから、おいしいワインとおいしい料理の組み合わせは、楽しい食事をするにはとても重要です。
しかし、ワインも料理もそれぞれがおいしければそれでいいのか、というとそう単純でないことも知られています。その組み合わせに関しては「赤ワインと肉料理」「白ワインと魚料理」というのは、最も知られた定石の一つです。
でも、あなたはこう思ったことありませんか?
赤ワインと魚料理を合わせてはいけないんだろうか?
白ワインと肉料理を合わせてはいけないんだろうか?と…
結論から言うと、赤ワインと魚料理でも相性の良い組み合わせはありますし、白ワインと肉料理でも合うものがあります。
そこで今回は、この定石外のワインと料理の組み合わせについてお話します。しかし、スペースの都合上、上記の両方をご紹介することはできません。ですから、今回は赤ワインと魚料理についてのみお話させていただきます。
なぜ、赤ワインと魚料理は合わないといわれるのか。どのような赤ワインと魚料理であれば合わせやすいのか。また、イマイチだなと思ったときは、どうすれば合うようにできるのか、についてお話していきます。
今日は赤ワインと魚料理で食事をしたいなと思ったときに、参考にしていただけると幸いです。
なぜ赤ワインと魚料理は合わないと言われるの?

赤ワインと魚料理でも良い相性の組み合わせはあります。しかし多くの場合、赤ワインと魚料理の組み合わせはあまり良い結果にはなりません。
では、なぜ赤ワインと魚料理は合わないのでしょうか。
赤ワインと魚料理が合わない理由は、大きく分けると2つあります。まずは、この理由から確認していきましょう。
両者の味のバランスが取れない

これはシンプルな理由です。赤ワインのほうが味が強いために、魚料理の繊細な味がわからなくなるということです。
赤ワインは種子、果皮などと一緒に醸造するため、これらから抽出される成分を多く含みます。そのため、香りが強く、味が濃く、渋みも多くなります。
それに対して魚料理は、脂分が少なくて味のインパクトが弱いものが多いため、赤ワインの風味の強さに対抗できません。
ですから、赤ワインと魚料理を合わせても両者の味のバランスが取れず、お互いを引き立て合うことなく、組み合わせの妙を楽しめないのです。
生臭さが引き立つ

言うまでもなく魚には独特の匂いがあります。時として、それはおいしそうな香りに感じることもあれば、不快な生臭さと感じることもあります。
赤ワインと魚料理の相性が悪いといわれるときの多くは、この生臭みを感じるときです。しかも、この生臭さの成分は1種類ではなく、大きく2種類に分けられます。それらを一つずつ見てまいりましょう。
トリメチルアミン
これは、魚が本来持っている生臭さの成分です。鮮度が良いときにはほぼ感じないのですが、水揚げから次第に増えていき、鮮度が落ちるほど生臭さが目立ってきます。
ですから、赤ワインと魚料理を合わせることで出てくる臭いではありません。
しかし、赤ワインと組み合わせたときのほうが目立ちやすいため、赤ワインと魚料理が合わないことの理由となっています。
なぜ赤ワインのほうが臭いを感じやすいかというと、白ワインのほうが生臭さを消す力が強いため、相対的に赤ワインを合わせたときに目立ってしまうのです。
では、なぜ白ワインは生臭さを消す力が強いのかというと、酸度が高いためです。
この生臭さの成分はアルカリ性なので、酸により中和させることで匂いが抑えられます。
これは、生牡蠣にレモンをかけると生臭さが消えることでも体験されているのではないでしょうか。
したがって、赤ワインよりも白ワインのほうが魚料理に合うといわれるのです。
ヘプタジエナールなど
もう一つが、ヘプタジエナールをはじめとする生臭さの成分です。こちらは、魚が本来持っている生臭さとは違い、ワインと組み合わせることによって出てきます。
魚には脂肪酸が含まれています。DHAやEPAというものはご存知でしょうが、これらが脂肪酸です。
この脂肪酸がワイン中に含まれるニ価鉄イオンと反応することによって酸化し、酸化脂肪酸へと変化するのと同時にヘプタジエナールなどが発生することで生臭さを感じます。
もう一つ、ワインに含まれている亜硫酸と脂肪酸が反応することでも、同様にヘプタジエナールなどと不快味が発生することも研究で明らかになっています。
この亜硫酸は、ワインの製造時に微量であるものの自然に発生しますが、多くは酸化防止剤として製造時に添加されるものです。
ここで、特に「赤ワイン」と書かず「ワイン」とだけ書いていることにお気づきでしょうか。
これは、ニ価鉄イオンや亜硫酸は、赤ワインだけでなく白ワインにも含まれていることを表しています。
ですから、赤ワインでも白ワインでも二価鉄イオンや亜硫酸を多く含むものは、生臭さが出やすいのです。
赤ワインと魚料理を組み合わせるときに注意すること
ここまで、赤ワインと魚料理が合わない理由を述べましたが、赤ワインと魚料理でも合う組み合わせがあることは先述したとおりです。
先程挙げた合わない理由に当てはまらなければ良い組み合わせになります。それぞれどのようなものを選べばよいのかを、具体的に説明してまいります。
赤ワイン
相性の良い赤ワインと魚料理を見つける際、2つの視点で見ていく必要があります。1つは味のバランスを取ること。もう1つは、生臭さを発生させないことです。この2つの視点から、魚料理に合わせやすい赤ワインについて考えてみます。
味のバランスを取る
繊細な魚料理と合わせるには、赤ワインも繊細なものを選ぶとよいでしょう。簡単にいうとライトボディのワインを選ぶということです。
では、ライトボディのワインを選ぶにはどうしたらよいのでしょうか。
ラベルに「ライトボディ」と表記されていれば話は簡単です。しかし、ラベルに味の表記がないワインも多くあります。そのときは、2つのポイントを見てください。
1つは冷涼な気候で栽培されたブドウから作られていること。もう1つが、ライトボディになりやすいブドウ品種から作られていることです。
では、冷涼な気候の栽培地というとどこなのでしょうか。
一つには、高緯度の場所です。国でいうと、北半球ではドイツ、南半球ではニュージーランドが高緯度にあります。
なぜ冷涼な気候ではボディの軽いワインになりやすいかといいますと、冷涼な土地では光合成があまり進まず、ぶどうの熟度が上がりにくいからです。ぶどうの熟度が低いと糖をはじめ味に影響を与える成分が少なくなります。結果、アルコールボリュームも低く風味も繊細なワインが出来上がります。
また、高度が高い栽培地も冷涼になりやすいので、ワインの説明に高高度で栽培されたブドウであることが記載されていれば、ライトボディの可能性が高くなります。
次に、ライトボディになりやすいブドウ品種についてです。
代表的なものが「ピノ・ノワール」や「ガメイ」という品種です。これらは共に渋みが少なく、穏やかな味わいのワインに仕上がるので、魚料理と合わせやすい品種といえます。
生臭さを抑える
先程、魚の脂肪酸と合わさることで生臭さを発生する成分として、ワイン中に含まれる二価鉄イオンと亜硫酸を挙げました。
ですから、これらが含まれない、もしくは少ないワインを選べば生臭さは発生しづらいということになります。
まず、亜硫酸に関してはラベルに記載しているワインが多くあります。「亜硫酸無添加」との表記があれば生臭さの出にくいワインということですので、魚料理と合わせるのなら候補とするのがよいでしょう。
しかし、残念ながらワインを選ぶ際に鉄分の含有量の目安となるものはありません。
実際に開けてみないことには確かめられませんので、鉄分の少ない赤ワインを選ぶというのは事実上不可能といえます。
魚料理
今度は逆に、赤ワインと合わせやすい魚料理がどのようなものか見ていきましょう。こちらも先程と同様に「味のバランスを取る」「生臭さを抑える」という点で見てまいります。
味のバランスを取る
まずは魚自体の話です。
赤ワインに合わせる際は、赤身の魚を選んでください。白身に比べ赤身のほうが、旨味が多く脂もしっかりしていますので、赤ワインの風味とのバランスを取りやすいです。
また、マグロやカツオなどの赤い色の成分である「ミオグロビン」は鉄のような風味が少しあり、これが赤ワインの味わいを引き立てます。
続いて味付けです。
赤ワインにはシンプルな味付けよりも、しっかりした味付けのほうが合わせやすくなります。
といっても、あまり濃い味付けでは魚の味が消されてしまいますので、ほどほどのものがよいでしょう。
例えば、トマトで煮込んだり、トマトソースをかけたりする料理は、トマトの旨味や酸味がワインとの良いつなぎ役になりますので、赤ワインと合わせる時の定番の料理法といえます。
生臭さを抑える
生臭さが出ないようにするには、調理にも気を配ってください。
まずは、加熱調理をすることです。熱を加えることで魚の臭みが飛ぶことがわかっていますので、刺身やカルパッチョといった魚を生で食べるものより、焼いたり煮たりして加熱するほうが生臭さを抑えられます。
さらに、この調理の際にワインなどの酒類を使うと、アルコールが蒸発する際に魚の臭みも一緒に飛ばしてくれるので、より臭いが気にならなくなります。
加えて、冷たい料理よりも温かい料理のほうが、白ワインと比べて高い温度で飲み、味わいもしっかりしている赤ワインのおいしさを引き出してくれます。
もう一点、油脂類を使った料理にすることです。
バターやオリーブオイルなどの油脂類を使用すると生臭さが抑えられることがわかっています。
これは、油脂が魚をコーティングすることで、魚の脂の酸化を防ぐことができるからです。また、生臭い匂いをオイルに閉じ込めて、揮発するのを防いでくれる効果もあるといわれています。
合わせやすい条件
| 赤ワイン | 魚料理 |
| ・高緯度の栽培地のもの ・高高度の栽培地のもの ・「ピノ・ノワール」「ガメイ」などのライトボディになりやすい品種で作られたもの ・亜硫酸を無添加、もしくは使用が少量のもの | ・赤身の魚 ・濃い味付けのもの ・加熱調理したもの ・調理にアルコールを使用したもの ・調理に油脂類を使用したもの |
赤ワインと魚料理の相性が良くなる3つの方法

これまで、赤ワインと魚料理を合わせる際に、それぞれどういう点に注意すればよいかお伝えしました。
それでも、食べてみたらあまりしっくりこない、ということがあるかもしれません。
そのようなときのために、料理に後から手を加えることで両者が合いやすくなる方法をお伝えします。
味のバランスを取る
赤ワインも魚料理も合いやすいものを選んだとしても、今ひとつ味のバランスが取れていないのであれば、そのときは料理にチーズをかけるのがおすすめです。
魚を食材として選び、その味を活かすように調理している以上、このような場合のほとんどはワインの味に料理が負けてしまっている状態だと思います。
この状況では旨味を加えることで、料理がワインに近づいていきます。
その方法としては、いわゆる「粉チーズ」をかけるのが手軽でもあってよいでしょう。
ただし、一般的に出回っている「粉チーズ」は塩分が強いものがほとんどで、料理にかけると塩辛くなってしまうことがよくあります。ですから、このようなときのために、一般的な「パルミジャーノ・レッジャーノ」よりも、塩分が控え目な「グラナパダーノ」という種類を使った粉チーズを用意しておくのをおすすめします。
逆に、ワインが料理に負けてしまっている場合は、レモンなど柑橘類の果汁をかけるとよいでしょう。
レモン果汁などは魚の生臭みを消す以外にも、塩気や旨味を抑える働きもありますので、ワインの繊細な味に寄せていくことが可能です。
生臭さを抑える
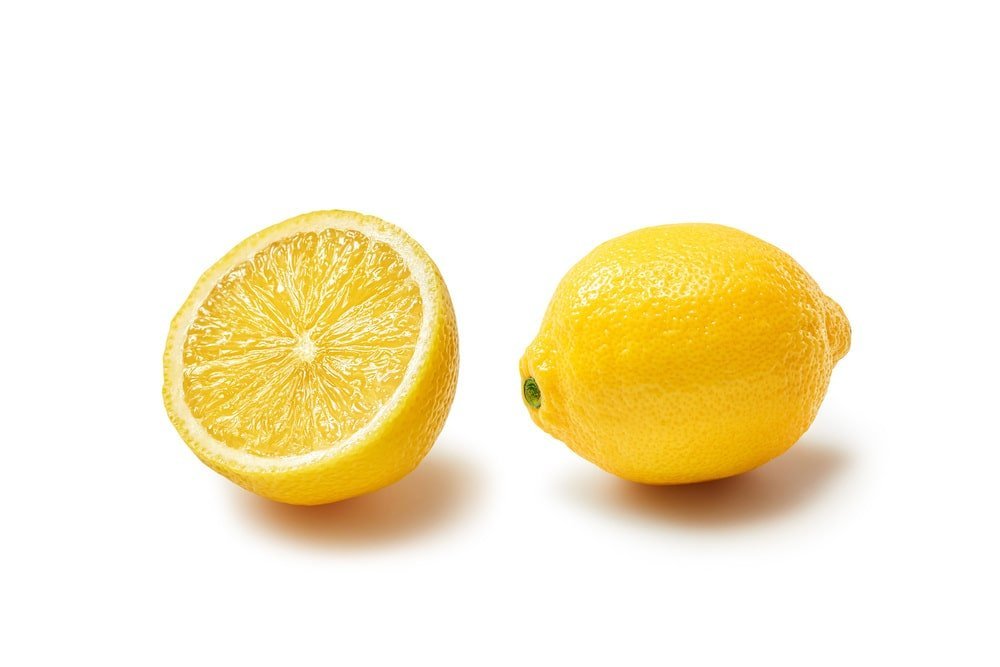
次に、相性が良いはずの赤ワインと魚料理を組み合わせたのに、生臭さが気になるときのおすすめの方法です。
酸味を加える
酸が魚の生臭さを消すことは、すでにお伝えしているとおりです。
しかし、酸には別の働き方で生臭さを抑えることもできます。
これは、レモン果汁などの酸がワイン中の鉄分とくっつくことで、他の成分と反応するのを防いでくれるというものです。
この働きにより、酸化脂肪酸との間でヘプタジエナール等の不快な臭いの発生が抑えられます。
もし、レモン果汁などをかけても味に違和感なく食べられる料理でしたら、酸味を加える方法がよいでしょう。
ただし、先述のとおりレモン果汁などは料理をさっぱりさせる効果がありますので、それで味のバランスが崩れてしまうことがあります。その際には、次の方法がおすすめです。
油脂を加える
こちらも、先程調理法のところでお伝えしましたが、油脂類には生臭さを抑える働きがあります。
ですから、生臭さを感じる際には後から油脂類を加えることでも臭いを抑えられます。
バターやオリーブオイルの他にも、サワークリームなど選択肢は多くあります。
これらを料理との相性を考えて使うと、調味料的に料理の味の幅を広げられ、より楽しい食事になるでしょう。
まとめ
今回は、赤ワインと魚料理との相性についてお話してまいりました。
一般には合わないとされる赤ワインと魚料理ですが、合わない理由を知ったうえでそれらを避け、それぞれの選択を間違えなければ、おいしく合わせられることがおわかりいただけたかと思います。
赤ワインを選ぶ際はライトボディのものを、その選び方としては高緯度地域などの冷涼な気候で作られているものや、繊細な味のワインになりやすい品種で作られたものを選ぶことです。
魚も、味のしっかりしたものを選び、加熱調理して味付けを濃い目にするのがコツでした。
それでもしっくりこない時には、チーズや酸味、油脂類を加えることで、より良くさせることも可能です。
ワインと料理は、意外な組み合わせが驚く結果になることもよくあります。今回のお話を参考にして、赤ワインと魚料理のおいしい組み合わせを見つけてください。