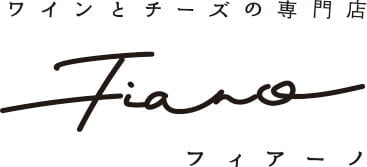みなさんこんにちは。日本でも人気のイタリアワイン。
誰しも一度はキャンティやバローロというワインの名前を聞いたことがあると思います。
イタリアはフランスと肩を並べるワイン大国。歴史は古く紀元前までさかのぼり、イタリア人の生活の一部として発展してきました。
日本同様に南北に長い地形を活かして土地の個性にあった多様なワインができあがります。今日はイタリアワインについて深く探っていきたいと思います。
イタリアワインの歴史を振り返る

イタリアワイン文化の歴史はローマ人から
イタリアワインは古代ローマ人がその基礎を作ってきました。
ローマ帝国の発展と共にイタリア全土にワイン文化が普及していきました。
暗黒の時代から
成熟したワイン文化は一度、民族の侵攻や西ローマ帝国の崩壊により衰退しました。
又、イスラム教徒に支配された地域もあり、ワイン造りが禁止される事もあったようです。
しかし、キリスト教の修道院ではひそかにワイン造りが行われます。
キリスト教徒にとって「キリストの血」であるワインはかかせないもの。
ワインを造り続けた徐々に修道院はワイン造りの知識と技術が高くなり、高品質のワインができるようになり技術は継承されていきました。
ルネッサンス期にワイン文化が復興
ルネッサンス期にはいると東欧との貿易のパイプが強くなり、巨万の富をもつ一族がでてきます。ワインは宗教的な飲み物から、庶民の食事の一部へと変わっていきます。文化的な喜びを与えてくれる産物へと変化しました。
この頃の文献にはワインに関する著述が多く見られるのがその証拠ですね。
各地でワイン文化が盛んになる
18世紀後半から19世紀後半にかけては各地で銘醸ワインが誕生していきます。
シチリアでは酒税強化ワインのマルサラ酒が世界的な成功をおさめました。
ピエモンテのバローロは甘口ワインから長期熟成の辛口ワインへなり
キャンティ地方では現在のキャンティの基礎となる品種構成が完成。
ヴェネト州の瓶内二次発酵ワインやプロセッコなど
続々と素晴らしいワイン達が開花していきました。
フランスのフィロキセラの被害により
1863年フランスではフィロキセラという害虫により壊滅状態におちいります。
まだ被害を受けていなかったイタリアワイン界は好景気で湧きました。
ただ長くは続きませんでした。
フランスでアメリカ台木によるフィロキセラ対策が発見され、たちまちフランスワインが復活します。
20世紀にはいると今度はイタリアがフィロキセラの被害をうけるようになりました。
その頃は世界恐慌の影響もあり、再びイタリアワインは衰退の一途をたどります。
多くのぶどう畑は荒廃し、長年の伝統や技術も失われていきました。
第二次世界大戦後にイタリアは経済成長したが……
この時代のイタリアワインは量より質。ピザ屋などで飲む、安い酒というイメージ。高級な飲み物ではなく大衆の酒として飲まれていました。
イタリア南部ではワインは輸出用の質のあまりよくないワインを大量に生産していました。
伝統的で高品質なワイン産業にもどそうと、イタリア政府による品質を良くする働きもありましたがうまく作用しませんでした。
イタリアワインのルネッサンス
ルネッサンスとは日本語で「文化復興」と訳されます。ローマ帝国の崩壊後は小さな自治国家の集まりであったイタリア。宗教的な支配からより人間らしい暮らしをもとめてルネッサンス(文化の復興)が始まっていきます。
ワイン界でもフィロキセラ後に一気に衰退、荒廃したワイン文化を取り戻す動きが始まります、それが1970ごろのイタリアワインのルネッサンスです。
イタリアワインの近代化
意欲的な一部の生産者の一団が世界に通用する高品質ワインの生産に乗り出します。イタリアワインの巨匠とよばれるアンティノリやガヤなどが自発的に始めました。
具体的にはフランスの最新技術をとりいれて、品種も海外品種も積極的に採用していきました。従来の殻をやぶって造られたイタリア近代ワインは世界的に注目を集めました。
メチルアルコール混入事件により高品質への道
近代化を図ったイタリアワインでしたが、一部の安ワインにメチルアルコールという有害物質が含まれており死亡者がでました。この事件でイタリアワインは大打撃を受けます。
これによりイタリアワインは高品質ワインへと舵をきって邁進していきました。
衝撃的な事件でしたが現在では信頼も回復、品質の高いワインを造り続けています。
イタリアワイン産地を知ろう

イタリアワインは変化にとんだ気候による多様性があります。山岳地帯と海岸線の間にある傾斜では、山と海との影響を受け、北部は石灰質土壌で南部は火山質土壌。又、1000以上のぶどう品種があります。
北西部
ピエモンテを中心とする北西部。ロンバルディア州やヴァッレ・ダオスタ州があります。しっかりとした赤ワインを産出する地域。タンニンが力強いネッビオーロ種の「バローロ」や「バルバレスコ」はポテンシャルの高いワインです。長期熟成にむいた世界的にも有名なワイン。ブレンドしたワインもありますが単一ワイン文化が根付いています。乳製品や白トリュフなどの美食の郷としても有名。
北東部
水の都ヴェネト州やフリウリ州がある地域。ロミオとジュリエットの舞台にもなった地域です。軽やかで気品があり繊細な白ワインを造っています。
食前酒や軽めの料理にはぴったり。フレッシュでフルーティーな「プロセッコ」は世界3大スパークリングワインと言われています。赤ワインも軽やかな味わいのものが多いですね。
中央部
トスカーナ地方を有する中央部はイタリア第一のワイン産地。
この地方ではイタリアの代表品種でもあるサンジョーベーゼ種から造った「キャンティ」があまりにも有名。ワイン造りの技術は日々進化しています。近年ではスーパータスカンといわれる、ボルドー品種をつかった近代ワインも高評価を得ています。

南部
カンパーニア州やプーリア州など個性的な州がひしめく地域。プリミティーヴォ種やネロ・ダーヴォラ種などコスパがいいワインの宝庫。
酒精強化ワインのマルサラも有名です。高価なワインはあまりありませんが、この地域でしか栽培されない多彩な品種が個性を発揮しています。
近年ではシチリア島の火山土壌をいかしたエトナ地区なども注目を浴びています。これからの産地ですね。
土着品種の宝庫!イタリアワイン品種を知ろう
イタリアワインの代表的な赤ワイン品種
ネッビオーロ
長期の熟成に適したポテンシャルの高い品種。深いガーネット色をしたぶどうでヴォリュームのあるタンニン(渋味)と酸味があります。スミレやバラのような芳醇な香りがあり高貴なイメージをたたえます。
バルベーラ
イタリアで生産量の多い土着品種。果実味のあるジューシーな酸が特徴でタンニンは軽やか。他の品種とのブレンドで樽熟成やスパークリングまで幅広いワインができあがる。
コルヴィーナ
アマローネという陰干ししたぶどうを熟成させる伝統的なワイン。その主要品種としてコルヴィーナがあります。とても豊かな果実味にしっかりと酸味がある存在感のあるぶどう。
サンジョベーゼ
イタリアワインの代表格キャンティの主要品種。軽い酸味とタンニンのバランスがいいですね。香りはスミレやチェリーのようなかわいらしい香り。イタリア現地で愛されている品種でデイリーワインにも使われています。イタリアでトップの栽培面積があり風土になじんだ品種ですね。
モンテプルチアーノ
果実味がしっかりとあり酸味は少なくタンニンが豊富。日本でもファンが多い品種です。トスカーナにある同名の街が名前の由来で、サンジョベーゼに続いて栽培面積が広くイタリアではおなじみのぶどう品種。
アリアニコ
酸とタンニンが力強いしっかりとした味わいをもった品種。火山地帯で造られることが多くパワフルなワインに仕上がります。主にイタリアの南部カンパーニュ州やバジリカータ州で栽培されています。
ネグロアマーロ
豊富な果実味にパワフルな酸味とタンニンのあるぶどう。イタリア語で「黒く苦い」という意味で、見た目も黒に近い濃い紫からもポテンシャルを感じる品種ですね。渋味はやわらかさがあるので初心者の方でも比較的飲みやすいおすすめの品種です。
ネロ・ダヴォラ
イタリアの南、シチリア島の主要品種。島の太陽を感じるしっかりとした果実味とタンニン。酸味はすっきりとしてどことなく海のようなミネラル感を感じるワインができあがります。酒精強化ワインのマルサラ酒でも使われている品種。
イタリアワインの代表的な白ワイン品種
ガルガネガ
皮が厚くジューシーな果実を実らせるガルガネガ。熟成により洋ナシやパインなどのトロピカルな香りがでてくるぶどう品種。味わいもふくよかです。特にソアーヴェ地区ガルガネガは火山土壌の影響でミネラル感を感じられます。
ヴェルナッチャ
フルーティーで華やかな果実味をもった品種。非常に繊細ではかなさを感じるフローラルな香りが特徴です。通称「ヴェルナッチャ・ディ・サン・ジャミ-ノ」と呼ばれています。古い歴史のある品種で13世紀には貴族に愛飲されていた品種でしたが衰退していました。近年に再興を手掛けられたぶどう品種です。
グレコ
ワインにするとモモやアプリコットのような香りがある品種。力強い酸味と豊かな果実味が特徴で、熟成が進むとはちみつやナッツ、ハーブなどの香りがでてきます。グレコはギリシャを意味する名前。古代ギリシャより持ち込まれた品種と言われ、主にカンパーニュ州で生産されています。
フィアーノ
香り高い品種ではちみつのようなアロマが特徴。ナッツやアーモンドの香りもあり非常に複雑な織り交ざった芳香をもっています。ミネラル感や酸味もしっかりと感じられる品種。
主にシチリア島やカンパーニュ州で作られています。
コルテーゼ
柑橘系のさわやかな香りと心地よい酸味をもった品種。ピエモンテの「カヴィ」という辛口ワインの品種でバーニャカウダとの相性は抜群。酸味が強く果実味のあるワインができるのでオイルを使う料理をさっぱりと味わえます。オリーブオイルをたっぷり使うイタリア料理と相性は本当にいいですね。
トレッビアーノ
柑橘系や青りんごのようなさわやかな香りのあるぶどう。フルーティーな味わいに加え若干の果皮の苦味を感じるのが特徴です。フレッシュな辛口ワインができあがります。栽培がしやすくイタリア全土で栽培されコスパのいいワインができあがります。
これが代表的なイタリア銘醸ワインだ!

イタリアワインには世界的にも有名な銘醸ワインが多数あります。みなさんも一度は聞いたことのあるワインがあるかもしれません。
バローロ
バローロはピエモンテを代表する王のワインと呼ばれています。ぶどう品種はネッビオーロ種の単一。バローロを名乗るにはバローロ村を含む11の村いずれかの産地であることが必要で、品種や産地なども厳格な基準が設けられています。
少しオレンジを帯びたガーネット色でスミレやバラのような芳香。淡い色ですが強い酸味とタンニンをもつ長期熟成タイプのワインです。大樽で仕込むのが伝統的な技法。
近年では華やかな香りと果実味をもったフレッシュなタイプもでてきています。
バルバレスコ
こちらもピエモンテの代表的なワインで女王のワインと呼ばれています。バローロと同じネッビオーロ種。産地は近いですが醸造過程がことなるので違った味わいになります。赤ワイン醸造過程で果皮ごと漬け込む作業がありますがその期間がバルバレスコは短かくとられています。酸味やタンニンがやわらかく、繊細でエレガントな仕上がりになります。こういったところが女王とよばれる所以ですね。
キャンティ
果実味豊かで程よい酸があるのみやすいスタイルの赤ワイン。サンジョベーゼ主体で親しみやすいワインです。19世紀ごろ飲みにくいとされていたサンジョベーゼを美味しく飲めるブレンド比を発見したリカーゾリ男爵という人物がいました。それがきっかけで飲みやすい愛されるワインにまでなりました。多くの生産者と種類があるワインです。
格付けってイタリアワインにもあるの?
実はイタリアワインにもフランスワイン同様に格付けが制定されています。
1963年に「DOC(原産地呼称管理法)」というワイン法が完成しました。
「DOC(原産地呼称管理法)」
生産地、栽培方法、ぶどう品種、最大収穫量、最低アルコール度数、熟成方法などを厳守した規定にのっとったワイン。品質の証明としてもちいられています。上級から以下のように4段階にわかれています。
・D.O.C.G.
・D.O.C.
・I.G.T.
・VdT
「DOP(保護原産地呼称ワイン)」
近年2010年にEUのワイン法にあわせて「DOP(保護原産地呼称ワイン)」が新たに制定されました。品質の基準は3つあります。
D.O.P.(保護原産地表示ワイン)
ぶどう収穫量やアルコール度数が厳格な規定でつくられている高級ワインが該当します。
ボトル上部に「D.O.C.G」や「D.O.C」と表記されているのは原産地呼称管理法(DOC)。上級ワインがこのランクに入ります。バローロやバルバレスコ、キャンティなどが代表的な「D.O.P.」ワインですね。
I.G.P.(保護地理表示ワイン)
産地のぶどうを85%以上使用することで生産地の名前をラベルなどに表示できます。
「D.O.P.」「I.G.P.」はラベル表記の義務があります。
Vino
生産者が自由に造れるワイン。ぶどう品種や生産地の規定はありません。比較的低価格なものも多いのですが、近年では少し事情がちがうようです。伝統やふるい規定にとらわれない造り手のこだわりがある高級ワインも造られるようになりました。
実は地域それぞれの格付けがあるんです
イタリア全土での格付けはDOCやDOPです。実はそれぞれの州や地域で独自に格付けやクラス分けを行っているものもあります。いくつかご紹介します。
キャンティ
キャンティには3つのクラスがあります。主な特徴をまとめました。
キャンティ
・サンジョベーゼ種を最低75%以上使用
・カナイオーロ種を最大10%まで使用可能
・トレッビアーノ種もしくはマルヴァジアを最大15%まで使用可能
・その他黒ぶどう品種を20%まで使用可能
・最低4か月熟成
キャンティ・クラシコ
・サンジョベーゼ種を最低80%以上使用
・その他黒ぶどう品種を20%まで使用可能
・最低11か月熟成
キャンティ・クラシコ グラン・セレツィオーネ
・自社畑生産のぶどうのみを使用
・サンジョベーゼ種を最低80%以上使用
・その他黒ぶどう品種を20%まで使用可能
・最低30か月熟成
ピエモンテの独自格付け「クリュ・バローロ」
フランスブルゴーニュではクリュといわれる単一畑のワインが最上級とされ人気です。近年ピエモンテの銘醸ワイン「バローロ」においても同じ動きがあります。
クリュは2000年には法的に認められ「MGA(Menzioni Geografiche Aggiuntive=追加地理言及)」という概念が誕生しました。それが「クリュ・バローロ」の基です。
現在バローロには181個の「MGA」がある
ブルゴーニュの「グラン・クリュ」や「プルミエ・クリュ」のようなヒエラルキーはありません。2015年にMGAについてまとめた大著「バローロMGA」で著者のアレッサンドロ・マスナゲッティ氏が独自に6段階の格付けをしています。
知っておきたいイタリアスパークリングワイン
ワインショップに行ってイタリアワインコーナーでみかける「スプマンテ」や「アスティ」などの単語。これらはスパークリングワインのことです、沢山あるイタリアスパークリングワインについて解説します。
スプマンテ
イタリアにおけるスパークリングワインの総称のことです。発泡性の低いものは「フリッツァンテ」と呼ばれます。商品名に「スプマンテ」がついていると「フリッツァンテ」以上の発泡性のあるスパークリングワインとなります。
フランチャコルタ
北イタリアのロンバルディア州で造られる高級スパークリングワイン。シャンパンとおなじ製法(瓶内二次発酵)でつくられています。シャンパンに次ぐスパークリングワインともいわれており、味わいも繊細でエレガント。シャルドネ、ピノ・ビアンコ、ピノ・ネーロという3種が主に使われる。
アスティ
北イタリアのピエモンテ州で造られるスパークリングワイン。モスカート・ビアンコ種を使ったとにかくフレッシュなスパークリングワイン。少し甘みがありアルコールも低めなので初心者でも非常に飲みやすいワインですね。微発砲のフリッツァンテスタイルもあります。
プロセッコ
シャンパン、カヴァと並んで世界3大スパークリングとも言われ近年人気のスパークリングワイン。ヴェネト州で生産されており、グレラ種を使用しています。やや苦みのあるドライな仕上がりのワインで、ほのかに甘みも残しておりバランスが良いですね。フリッツァンテスタイルもあります。
ランブルスコ
美食の都、エミリア・ロマーニャ州で造られるランブルスコ種を使った発泡ワイン。白やロゼもあるが日本では赤が有名。赤ワインを造る途中で炭酸ガスを溶け込ませ、程よいスパークリングワインができあがる。 辛口の「セッコ」中口の「アマービレ」甘口の「ドルチェ」がある。

イタリアにもあった!新酒を祝う習慣「ノヴェッロ」
フランスのボジョレー・ヌーヴォーのようにイタリアにも新酒を祝う「ヴィーノ・ノヴェッロ」があります。
その年にとれたぶどうを使いワインを醸造。個性豊かな産地が多くあるイタリアなので各地の味わいも千差万別。
熟成させないで飲む果実味豊かな味わいは飲みやすく、日本でも人気がでてきています。
ノヴェッロの解禁日は10月30日午前0時1分
以前は11月6日でしたがあたらしいワイン法の改定とともに政府がわかりやすく単純化させたようです。
イタリアワインのグレートヴィンテージ
ワインは生産年によって出来栄えが大きく変わります。良い年はあたり年やグレートヴィンテージと呼ばれ、熟成にも耐えるポテンシャルの高いワインが産み出されます。
ここでは熟成ワインの「バローロ」のヴィンテージチャートを参考にしました。3社のヴィンテージ評価を参考におすすめヴィンテージを掲載しました。ご参考までにご覧ください。
2016年
近年でいちばんおすすめの年です。まだ手に入りやすく価格の高騰もおさえられているヴィンテージかと思います。見つけたらすぐ買いですよ。
2010年
ここ10年では最高の評価を得ています。まだまだ手に入るレベル。これは手にいれなければ……
2007年
2010年に負けないくらいの高評価年。ここらあたりから上級バローロはかなり手に入りにくいですね。価格も上がってきます。
2004年
ぶどうの出来が良いのでクリュではないバローロを試してみるのも面白いかもしれません。ネッビオーロのポテンシャルを感じてみたいですね。
2000年、2001年
ヨーロッパ全土でめぐまれたヴィンテージですね。世界のコレクターがねらっているヴィンテージ。ふいにでてくる蔵出しワインなどをねらうしか手はありません。
最後に
いかがでしたか?イタリアワインの歴史から始まりみなさんに知ってほしいイタリアワイン情報をまとめてみました。
なんといってもイタリアワインの魅力は多様性にあります。色々な風土でできるイタリアワインはバラエティーに富んでいてどこか陽気なあたたかさを感じます。みなさんのお気に入りのイタリアワインを是非さがしてみてください。