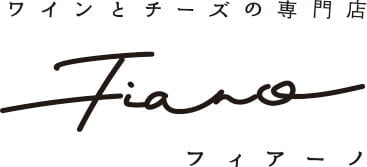「チーズ」は、私たちにとって非常に身近な発酵食品であると同時に、多くの人を魅了してやまない嗜好品でもあります。栄養価に富んでいるうえ、食味にも優れているチーズは、昔から多くの人に愛されてきました。
ここではこのチーズを取り上げ、その歴史と生い立ち、現在の姿や世界でのチーズの受け止められ方、そして日本のチーズの消費量について解説していきます。
チーズそのものの生まれ故郷とその歴史

チーズの歴史は非常に古く長く、その発生年を正確に把握することは極めて困難です。
世界に数多くある発酵食品のなかでももっとも古い歴史を持つものであるとされていて、紀元前5000年ごろに生じたものなのではないか、というところまでしかわかっていません。
これを前提として、チーズの発生時期や発生のときのエピソードについて掘り下げていきましょう。
ご存じの通り、チーズは「乳製品」です。そのため、チーズの前にまず「乳」があって、それを飲む習慣があります。動物の乳を飲むというライフスタイルは紀元前6000年ごろに生まれたと考えられています。
2012年には、紀元前5000年ほどの時期の遺跡から、チーズを作っていた痕跡が見られたと報告がなされました。この遺跡では、「大量の乳脂肪分が残っている土器」が発見されていて、この土器が、チーズの制作過程の一つである「カードとホエイの分離」に使われたのではないかと推測されています。
また紀元前4000年ごろの壁画においては、「乳を搾り、チーズを作っている過程」が描き出されています。だれもが歴史の授業で習う古代メソポタミア時代のものであり、この時期にはすでにチーズが作られていたと考えられています。
ちなみに紀元前2000年ごろの逸話として、「昔、羊の胃袋に乳を入れて砂漠を渡った人間がいた。夕方になってこれを飲もうとしたが、中からは乳は出てこない。残っていたのは、白い塊と水に似た水分だけであった。しかしこの白い塊を食したところ、大変に美味であった」というものが残っています。これはアラビアの民話なのですが、チーズを作る際に使われる羊の胃袋の酵素(レンネット)の存在を示唆する逸話だといえます。
そして紀元前1500年ごろには、現在も愛されているフェタチーズの製造が始められました。ギリシアで生まれたこのチーズは、その強烈な酸味によって非常に個性的なものに仕上げられています。なおこの「ギリシア産のフェタチーズ」は、今の日本でも通販などで気軽に買うことができます。
ここまで、チーズの歴史についてみてきました。現在わかっている文献や研究から考えれば、チーズの歴史は紀元前5000年くらいにあるといえるでしょう。
もっとも、このような歴史の流れのどこを切り取って「起源」とするかという問題はあります。「紀元前5000年ごろにチーズを作っていたであろう痕跡はあるものの、しっかりとした資料として残っているのは、古代メソポタミアで見つかった壁画からだ」と考えるのであれば、チーズの起源は紀元前4000年ごろということになるでしょう。
それ以降も綿々とチーズの歴史は続いていく
チーズの歴史として、チーズの発生時期~紀元前までの歴史を追ってきました。
しかしチーズの歴史は、それ以降も綿々と続くことになります。
紀元前100年~50年くらいの間に、スイスでもチーズが作られるようになります。今も「チーズ大国」として知られるスイスですが、このころにはすでにチーズを作る文化が始まっていたのです。
スイスチーズについてはこちらの記事も詳しく執筆していますので合わせてお読みください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://fiano.co.jp/types-and-characteristics-of-swiss-cheese/ target=]
そして879年に、イタリアでゴルゴンゾーラチーズが誕生します。今も「世界三大青かびチーズ(残りの2つは、スティルトンとロックフォール)」として取り上げられるこのゴルゴンゾーラチーズは、1350年近い歴史をもっているわけです。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://fiano.co.jp/about-gorgonzola/ target=]
1400年~1500年ごろは、ハード・セミハードチーズに分類されるチーズが本格的に作り始められるようになった時期です。エメンタールチーズやチェダーチーズといった、今でも多くの人を魅了しているチーズは、この時期に生まれました。
そして、1791年に、「カマンベール」が歴史のなかに登場します。カマンベールは、ノルマンディ地方のカマンベール村にいた一人の農婦マリー・アレルによって生み出されました。
彼女の生み出すチーズのおいしさは、衝撃をもって受け入れられました。そのチーズはマリー・アレルの宝物となり、そしてそのレシピは彼女の子孫に代々受け継がれていくことになります。
なお、このカマンベールは、時の権力者ナポレオン3世にも献上され、それ以降もずっとパリのチュエルリー宮に貢物としてささげられるようになりました。
ちなみに、現在でこそ「たくさん流通していて、保管もしやすく、値段も安い」として多くのスーパーに置かれている「プロセスチーズ」ですが、これが登場したのはわずか100年ほど前のことです。それまでチーズといえばナチュラルチーズが中心でした。
1911年にスイスでようやくプロセスチーズが量産されるようになり、これも世界に広まっていくことになります。
プロセスチーズについてはこちらの記事に詳しく執筆していますので合わせてお読みください。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://fiano.co.jp/types-of-processed-cheese/ target=]
チーズが日本にやってきたのはいったいいつごろ?

上では「世界のチーズの歴史」に焦点をあてていたため、あえて「日本でのチーズの歴史」については解説してきませんでした。
ここからは日本に注目をし、「日本とチーズの歴史」について解説していきます。
日本にチーズが入ってきたのは、645年ごろのことだと考えられています。
遣唐使が大陸に渡りその文化を日本に持ち帰ろうとしていたこの時代に、百済から帰化した人間の子孫によってチーズの文化がもたらされました。ちなみにこの人間の名前も分かっていて、「善那(ぜんな)」という名前だったとされています。
牛乳を使って作られた「酪」と「蘇」が時の天皇・孝明天皇に献上されましたが、このうちの「蘇」がチーズの原型であったと考えられています。もっともこのときの「蘇(チーズ)」は、牛乳を煮詰めて、それを固めたものであったとされていて、現在のチーズとはかたちが異なります。
飲食物の普及には、しばしば時の権力者の意思が反映されます。蘇(チーズ)もまた例外ではありませんでした。
897年~930年にわたって天皇を務めた醍醐天皇は、酪農に対して強い関心を払ったとされています。そのため、酪農を推奨し、各国に銘じて蘇(チーズ)を天皇家に納めさせる「貢蘇の儀(こうそのぎ)」を行うように命じました。
ただ、日本におけるチーズの歴史は、武家社会に移り変わったことでその進展が途絶えてしまいます。
日本の歴史においてチーズが再び脚光を浴びるようになったのは、1728年のことでした。
当時の将軍であった徳川吉宗公が、オランダ人のアドバイスに従ってインドから白牛を3頭仕入れ、その牛の乳を使ってチーズを作り始めたのです。もっともこのときのチーズは、「現在におけるバターに近かったのではないか」とする説もあります。
現在でもチーズの名産地として知られている北海道において、1875年に本格的なチーズ作りが始められたことが記録に残っています。
「北海道開拓移民」「開拓使」などの名称で物語の題材などに取り上げられることもある開拓民ですが、彼らは自然との壮絶な戦いのなかで、数多くの功績を残していきます。
そのうちのひとつが、この「チーズ」でした。
北海道開拓庁にてチーズと練乳を試しに作ってみたとされていて、これが日本のチーズ製造の始まりだといわれています。
なお、非常に知名度の高い雪印乳業(旧・北海道製酪販売組合連合会)と明治乳業は、昭和に入ってからともにプロセスチーズを作り始めるようになります。また、世界大戦が終わったのちには、日本でもブルーチーズなどがみられるようになりました。
[sitecard subtitle=関連記事 url=https://fiano.co.jp/how-do-you-write-cheese-in-kanji/ target=]
各国のチーズの歴史と、日本の話
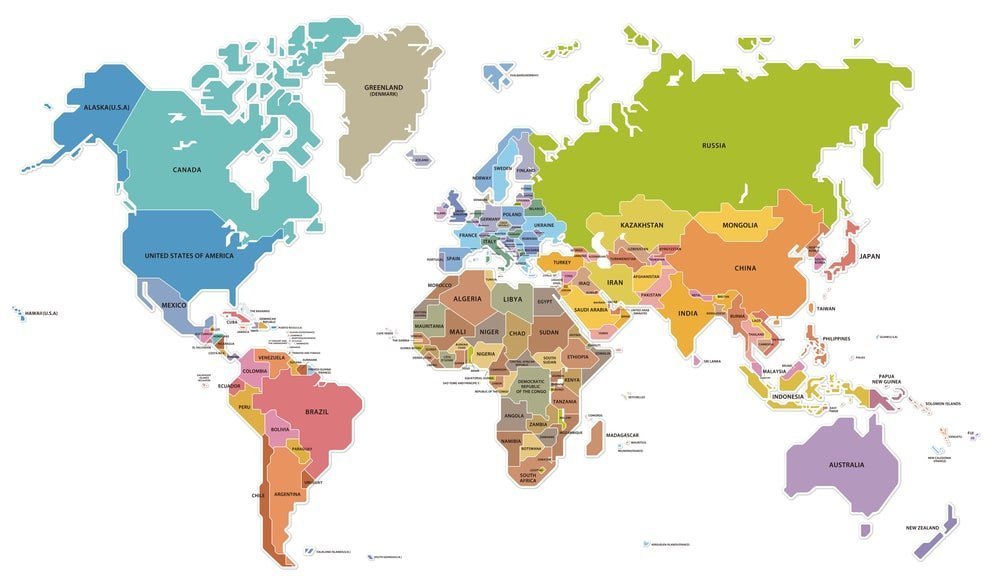
ここからは、さらに詳細に、「各国におけるチーズの歴史」について解説していきます。
ギリシア
上でも述べたように、紀元前から今につながる「フェタチーズ」を作り上げた国です。また、叙事詩「オデュッセイア」でも、チーズが取り上げられています。キュクロープス(一つ目の巨人)がチーズを作り上げるシーンなどがそれで、チーズが昔からギリシアの人にとってなじみ深いものであったことが分かります。
インド
意外に思われるかもしれませんが、インドもチーズにおいて長い歴史を持っています。リグ・ヴェーダという書物のなかにもこのチーズが取り上げられています。
なお、東北大学では、インドの最古の文献に出てきた乳加工品を再現しようとする研究も行っていました。
イギリス
ローマ帝国時代からチーズが作られていたとされるイギリスでは、1日に2回乳しぼりをする「ミルクメイド」が働いていました。彼女たちの絞った乳は、チーズやバターなどにも加工され、保存食として利用されていくことになります。
イギリスのチーズの種類や歴史についてはこちらの記事も合わせてお読みください。

日本
かつては、「食べやすくくせのないチーズ」が好まれた日本でしたが、現在は個性派のチーズも多く消費されるようになっています。
日本におけるチーズの需要・消費量は年々増え続けています。
多少の増減はあるものの、基本的には2009年から2020年までその消費量は右肩上がりに増え続けています。2009年と2020年を比べてみた場合、その消費量はなんと1.5倍近くにもなっています。
今後もこのような展開は続いていくと思われます。
今から何千年も前に、地球に誕生した「チーズ」。
このチーズは長い歴史のなかで、かたちを変え、姿を変え、製法を変え、それでもなお、令和の今の世の中でも私たちに愛され続けています。
出典;
農林水産省「チーズの需給表」
本間るみ子「知っておいしいチーズ辞典」p20-21